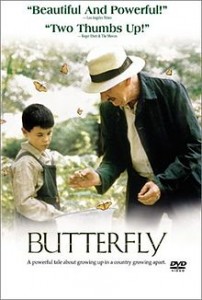 この映画を『ベル・エポック』(1992年)と『みつばちの囁き』(1973年)と併せて観ると、スペインの1931年の第二次共和制の樹立から、1936年の内乱の勃発と、ファシストが政権を取ってからの苦しい沈黙の時代がよくわかる。『ベル・エポック』は共和制樹立を描き、『みつばちの囁き』は1940年代の沈黙の時代を描く。この『蝶の舌』は1936年の内戦に至る過程を描いている。映画が作成されたのも、フランコ政権が倒れ民主主義が戻ってきた1999年であるから、スペインの芸術家も沈黙を破り、自分を守るシンボリズムも捨て、自分の訴えたいことを率直に表現していると言える。
この映画を『ベル・エポック』(1992年)と『みつばちの囁き』(1973年)と併せて観ると、スペインの1931年の第二次共和制の樹立から、1936年の内乱の勃発と、ファシストが政権を取ってからの苦しい沈黙の時代がよくわかる。『ベル・エポック』は共和制樹立を描き、『みつばちの囁き』は1940年代の沈黙の時代を描く。この『蝶の舌』は1936年の内戦に至る過程を描いている。映画が作成されたのも、フランコ政権が倒れ民主主義が戻ってきた1999年であるから、スペインの芸術家も沈黙を破り、自分を守るシンボリズムも捨て、自分の訴えたいことを率直に表現していると言える。
1936年、スペイン、ガリシア地方の片田舎の町。喘息持ちのモンチョは1年遅れて小学校に入学する。人見知りをしてなかなか周囲に馴染めないモンチョに、担任のグレゴリオ先生は優しく接してくれた。グレゴリオ先生は、子供たちに授業以外にも、人生、文学、愛など色々なことを教えた。先生は、生物を勉強するために子供たちをフィールドトリップに連れていく。蝶の舌の話に興味を持ったモンチョに、先生は顕微鏡で見せることを約束する。モンチョの兄アンドレも町のバンドに入れてもらい、いろいろ演奏旅行をすることで人生を広げて行く。モンチョの父は共和党派であり、母は共和党を信じないが、それが夫婦の絆には何の障害もない。父とグレゴリオ先生の間には友情と尊敬があった。
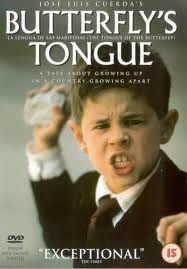 しかし、遂に町がファシストに乗っ取られる日がやってきた。それまで共和党の支持者であることを明らかにしていた父は一家を守るために、逮捕された共和党派の人々の見せしめに加担するために、町の広場に他の町民と出て行く。一家を守るために、母は逮捕された人々に罵声を浴びせかけ、それを黙って見ていた兄弟だが、アンドレは自分に優しくしてくれたバンドリーダーが、モンチョは自分の親友の父がその逮捕された人々の中に入っているのに驚く。その逮捕された人々の最後に並んでいたのは、グレゴリオ先生だった。父も苦しそうに罵倒を始める。母に促されて、モンチョは自分の大好きだった先生に、「赤!」「無神論者!」と罵倒し、自ら進んで石を投げつけるのであった。
しかし、遂に町がファシストに乗っ取られる日がやってきた。それまで共和党の支持者であることを明らかにしていた父は一家を守るために、逮捕された共和党派の人々の見せしめに加担するために、町の広場に他の町民と出て行く。一家を守るために、母は逮捕された人々に罵声を浴びせかけ、それを黙って見ていた兄弟だが、アンドレは自分に優しくしてくれたバンドリーダーが、モンチョは自分の親友の父がその逮捕された人々の中に入っているのに驚く。その逮捕された人々の最後に並んでいたのは、グレゴリオ先生だった。父も苦しそうに罵倒を始める。母に促されて、モンチョは自分の大好きだった先生に、「赤!」「無神論者!」と罵倒し、自ら進んで石を投げつけるのであった。
この映画で一番怖いのは、平和に暮らしていた町の人々が内戦で一転して敵味方に別れてしまうことだ。内戦が始まる前は、夫婦の間でも、家族でも、学校でも、教会でもそれなりの小さな問題や意見の食い違いがあった。しかし、町というコミュニティーはそんな小さな違いを乗り越えて互いに助け合うことで成立していた。しかし、中央の政権争いが段々過激になるにつれて町の人々の顔つきまでが変わってきて、最後は憎しみと怖れと戦いと投石でコミュニティーが破壊していく。ファシストと共和党の戦いは遥か彼方の政権中央部で行われている抽象的な争いではない。ここでは、昨日の隣人が今日の迫害者になる恐ろしい現実なのだ。
もう一つ怖いのは、子供が親の保身を恐れを敏感に感じ取り、親以上の過激な行動にでてしまうことである。映画では、両親は戦争も望まないし、誰をも傷つけたくないのだが、もし逮捕された共和党派の味方をしたら、明日はわが身だということがわかって、保身のための罵倒を行う。しかし子供はその親の怖れを敏感に感じ取って、親以上の行動に出てしまうのだ。自分の行為に対する結末がわからないだけ、コントロールがきかないのが怖い。
しかし、この映画は自分をあれだけ可愛がってくれたグレゴリオ先生に投石をするモンチョを責めているのではない。何が起こっているかわからないが敏感に何かが起こっていることを感じ取れる子供をそのように行動させる時代が悪いのだ。中国の文化大革命でも、カンボジアのクメールルージュでも、子供が大人たちを裁いている。その背後には子供たちをそうさせた何者かがいたのだ。
フランコの死は1975年、スペインが本当に民主国家として安定したのは1981年、反フランコ者の名誉が回復するのは2008年まで待たなければならない。スペインにはグレゴリオ先生のように、名誉を奪われて死んだ人々はたくさんいるのだろう。

スペイン内戦のころを舞台とした映画であれば、「パンズ・ラビリンス
El laberinto del fauno」はいかがでしょうか。この映画では女の子が主人公です。