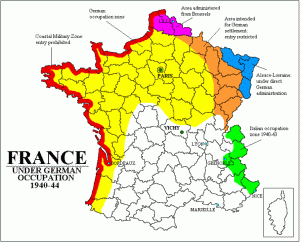2006年にアカデミー賞最優秀外国語賞候補にノミネートされた名作 『デイズ・オブ・グローリー』の成功の後で、夢よもう一度という感じで作られた続編の『Outside the Law』は、残念ながら前作には全く及ばぬ出来であり、柳の下に二匹のドジョウはいなかったようだ。
2006年にアカデミー賞最優秀外国語賞候補にノミネートされた名作 『デイズ・オブ・グローリー』の成功の後で、夢よもう一度という感じで作られた続編の『Outside the Law』は、残念ながら前作には全く及ばぬ出来であり、柳の下に二匹のドジョウはいなかったようだ。
監督は前作と同じラシッド・ブシャール、『デイズ・オブ・グローリー』でカンヌ最優秀男優賞を受賞した兵士役の3人の俳優が前作と同じ役名(メサウード、アブデルカダ、サイード)で出てくるが、続編では3人はアルジェリア出身の兄弟という設定である。前作でちょっと癖のあるマーチネス軍曹をやった俳優はその3人を追うフランスの捜査官として出演する。ただ1人前作の主要人物で同じくカンヌで最優秀男優賞を取ったヤッシール役のサミー・ナセリだけは出演していない。実は彼は『デイズ・オブ・グローリー』の出演の前後から、コカイン所持などを含めて何回か法律に触れ有罪判決を受けていたが、2009年には遂にナイフでの傷害罪を起こして逮捕されているので、そのせいであろう。
顔立ちも体型も違う3人の俳優が同じ部隊の兵士なら説得力もあるが、兄弟を演じるのはどうも違和感がある。いろいろな事件が降りかかって来るのも、同じ部隊の兵隊なら納得だが、3人の兄弟に次から次へと降りかかってくるのもあまりにも偶然すぎる。また、この映画は第二次世界大戦前から1962年の長い年月を2時間で描くので、今一つ上滑りで、掘り下げ方が浅いという印象を受ける。『デイズ・オブ・グローリー』の成功のあと、ラシッド・ブシャール監督はもっとエンターテインメントの要素を強くして、アクションシーンを投入することで興行的な成功も狙っているかのようだ。事実、この映画にはハリウッドの伝説的な映画『ゴッドファーザー』の影響が強く感じられる。しかしそのアクションシーンもなぜか今一つである。ハリウッド映画にもいろいろ批判があるだろうが、ハリウッドもいたずらにそのアクション映画のテクニックを育ててきたわけでない。アクションシーンでは、ハリウッドにはまだまだ及ばないというのを見せ付けられたような気がする。
この映画はアルジェリアの村で、3人の兄弟の父が所有する土地がフランス人と連帯するアルジェリア人に奪われて、一家で故郷を去るところから始まる。映画自体はフィクションであるが、実際にあった事件を背景に取り入れており、その例の一つがセティフの虐殺である。1945年5月8日、ドイツ降伏の後、アルジェリア人がフランス軍事基地のあるセティフ及び近隣で独立を要求してデモが行われたが、警察が介入する中でそのデモが暴動に姿を変えその鎮圧の過程で多数の人 間が殺害された。映画では、兄弟の父はその中で殺害され、次男のアブデルカダが逮捕されフランスの刑務所に送られる。
長男のメサウードはフランス軍兵士としてベトナムに出兵する。映画ではベトナムに送られたのは主にフランス植民地の兵士であると描かれている。実際に当時フランスは第一次インドシナ戦争を戦っていたが、その主力であるモロッコやアルジェリアおよびセネガル等の他の植民地人達の士気は低く、厭世気分が強かったらしい。結局フランスは1954年のジュネーヴ協定によりベトナムから手を引くことになる。
三男のサイードは自分たちの土地を奪ったアルジェリア人の地主を殺害し、母を連れて兄が囚われているパリに渡り、そこで酒場とボクシングのジムを始め、金儲けに専念する。やがて長男がベトナムから帰還し、次男が釈放され家族がようやくランスで再会する。
次男のアブデルカダと長男のメサウードは、パリでアルジェリア民族解放戦線(FLN)に参加したが、二人はメサウードが第二次世界大戦におけるレジスタンス運動やベトナム戦争で出会ったアルジェリア人で、今はフランス政府内部で働いている旧戦友を利用して、政府関係者を暗殺して行く。FLNの動きが過激になって行くにつれて、二人の行動もどんどん暴力的になって行く。
『デイズ・オブ・グローリー』の成功のあとたくさんの人々がラシッド・ブシャール監督に映画の中の人物はその後どうなったのか、と尋ねるので監督は続編を作成することにしたという。しかしこの映画は、FLNの暴力を否定しているのか、肯定しているのかわからない。多分否定しているのであろうが、暴力的なシーンを見続けるのはたまらない気持ちになる。またアルジェリアの将来に対する希望が見えない映画であった。素晴らしい名作の待望の続編が非常に暴力的で、見たあとで気持ちが暗くなるような作品であったことは残念であるが、これは独立に多大な犠牲を払い、現在でも政情不安定が続くアルジェリアの悲しい現実を投影しているのかもしれない。また、この映画の内容は歴史的に公平ではないと多くの人が抗議したという。いろいろな意味で賛否両論の映画だったようだ。この映画もアカデミー賞最優秀外国語賞候補にノミネートされた。