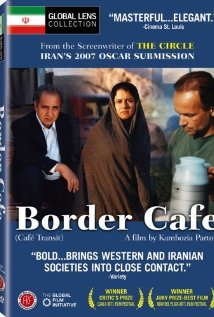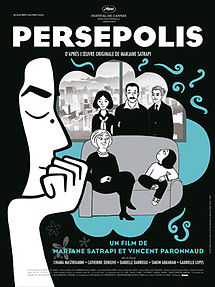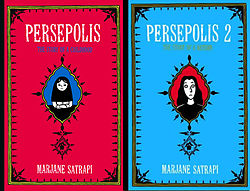見終わった後、すごい映画を観てしまったという想いが残り、胃がドンと突かれたようで言葉もなかった。こんな経験はめったにあるものではない。
見終わった後、すごい映画を観てしまったという想いが残り、胃がドンと突かれたようで言葉もなかった。こんな経験はめったにあるものではない。
この映画はイランの中産階級の夫婦の離婚裁判から始まる。妻のシミンは11歳のテルメーの将来を考えて海外移住を望んでおり、やっとのことで出国のビザが降りた。しかし夫のナデルはアルツハイマー(認知症)の父を置いて出国することができず、二人は離婚の道を選ぶ。しかし娘の親権をどちらが取るかということで、二人は争うことになり、その期間、シミンは実家に戻ることになる。
シミンは友人の妹である労働者階級のラジエーをヘルパーとして雇うが、彼女はナデルの父をベッドに縛り付けて外出してしまう。それを発見して激怒したナデルはラジエーを家から追い出してしまうが、その晩ラジエーは流産してしまう。ラジエーの夫のホッジャトは刑務所帰りの短気で暴力的な男で、ナデルを殺人罪で告訴すると共に、ナデル一家やナデルのために簡易裁判所で証言してくれた女教師を威嚇するという行動にでる。
この映画は階層や宗教心の深さの違う2組の夫婦の法廷での争いと、シミンとナデルの親権闘争という2つの主題を巧みな構成と全く無駄のない見事なストーリー展開で、一分も息をつくことを許さぬサスペンスで聴衆を最初から最後まで引っ張り続ける。一言で言えば、どこにでもいる人間の日常で簡単に起こり得る事件の謎解きである。トルコの監督で元写真家のヌリ・ビルゲ・ジェイランが完璧な画像を提供するのに対し、脚本家の経験豊かなこのイラン映画の監督アスガル・ファルハーディーは、完璧なストーリーテラーといえるだろう。しかし、この映画の本当の素晴らしさは、そのプロットの奥深くに隠されたメッセージである。
アスガル・ファルハーディーの作風を一言で言えば、聴衆に対する信頼である。ハリウッド映画によくある、bad guy, good guy の明らかな役分けや、プロットに対する至れり尽くせりの解説やhappy endingはここには全くない。監督がスプーンを聴衆の口まで運んできちんと食べさせてあげる映画ではないのである。聴衆はナデルがホッジャトと示談したのか、またそれが決裂して刑務所に送られたのか、あるいは流産の責任が彼にないと証明されて無罪放免になったのかはっきりとわからない。また親権はテルメーの選択に任されるが果たして彼女がどちらを自分の親として選ぶのかはわからない。またラジエーは本当にナデルのお金を盗んだのか、ナデルの父を縛り付けたのか、誰がナデルの父の酸素ボンベを開けて危険な状況を生み出したのか、シミンはどの国に移民しようとしているのか、などは全く説明されていない。監督の意図は、そんな説明は重要なことではないし、その解決は読者の考える力に任されていると主張したいようなのである。
アスガル・ファルハーディーはインタビューに答えて、「医者が診て余命一ヶ月の患者がいるとする。イラン人の医者は患者にあなたはまだ死なないと告げ、患者の親族のみに真実を告げるだろう。しかしスウェーデンの医者なら、患者に直接はっきりと余命一ヶ月だと告げ、心の準備をさせるだろう。どちらが正しい医者だとはいえない。大切なことは、あなたがどちらの医者を選ぶかということだ。」と述べている。彼はどこにでも起こり得る、どちらの結論にもなりえる事件を語ることにより、聴衆が何かを感じてくれることを祈っている。たとえ、聴衆の結論が彼の意図と違うことであっても、構わないのだ。聴衆がそれぞれの心で考え、感じてくれる限りは。
では彼がプロットの奥で伝えたいメッセージは何か?私はそれはイスラム教原理主義の名のもとに女性の生き方を縛っている社会への批判であると思う。ラジエーは宗教心の強い女性で、失禁したナデルの父の体を清めるためにも、宗教のオーソリティーに電話をかけ男性の老人の体を触っていいかどうかを尋ねなければならない。オーソリティーがそれを認めたのかどうか映画ではわからない。多分だめだと言ったのだろうが、ラジエーは老人を放っておくことができない。4歳になるラジエーの娘は「大丈夫。お父さんに告げ口しないわ」と言い母を安心させる。ラジエーがナデルのために流産したと100%思えないのにナデルのせいだと主張したのも、夫に殴り殺されるのを恐れたからである。しかし、嘘をついて多額の示談金をもらうと自分の娘に将来恐ろしい報いが来るとの怖れから、自分の危険を冒してまで真実を告げるのである。シミンも自分の娘がイランで朽ち果てるのを恐れて、すべてを捨てて海外移住をしようとしている。女の子を持つ母親がしなければならない難しい決断をこの映画は描いている。アスガル・ファルハーディーにも娘がおり、この映画ではシミンとナデルの娘テルメーを演じている。賢こそうな少女でベルリン映画祭でも最優秀女優賞を受賞している。アスガル・ファルハーディーも娘の将来に対する夢と、イランという体制の中で娘を育てなければならないという不安を同時に抱いているのであろう。
イランの現体制を批判する映画人は亡命したり、或いは刑務所に送られたりしている。アスガル・ファルハーディーも、2009年に起きた大統領選挙でマフムード・アフマディーネジャードの再選に反対する緑の運動に参加した芸術家を弁護したことにより、映画人としての活動権を剥奪された過去を持つ。彼はその後国内に留まりその制限の中で映画を作ることを決心しているようであるが、政府から弾圧されないように、ぬらりくらりと、うまく映画を作ることに成功している。まず、表立った宗教的な批判もないし、登場人物が体の接触をしないようにしている。すべての体制批判は、主人公のシミンを通して暗喩されるが、彼女は知的階級で少々身勝手な女性にも見えるような描かれ方をされている。「私はこんな環境で子供を育てたくありません!」と堂々と判事の前で述べる彼女だが、その環境とは頑固な夫との家庭を指すのかそれともイランの社会を暗喩しているのかは聴衆の解釈に任せられている。また繰り返し繰り返し、「シミンさえ海外移住という野望を持たなければ、こんな事件は起きなかったのだ。」という嘆きが囁かれる。しかしこの映画で本当に子供のためを思って行動しているのは、シミンとラジエーという二人の若い母親であり、シミンは実は非常に賢く他人の幸せを第一におき、自分を犠牲にする女性だということがわかってくる。ナデルの父も認知症でありながら、シミンに感謝しているというところが繊細に描かれている。
 別離は第84回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、イスラエルから出品され最終候補にノミネートされたFootnoteを破り、アカデミー賞を受賞した。イラン国内では宿敵イスラエルを破ったと大変な興奮だったそうだ。アスガル・ファルハーディーもこれでイランの体制内でも映画を作りやすくなったかとは思うが、「どうだ、イランは俺のおかげでイスラエルに打ち勝ったんだ」とは思ってほしくない。彼はそんな人ではないと信じたい。彼のオスカー受賞のスピーチは素晴らしかったからだ。
別離は第84回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、イスラエルから出品され最終候補にノミネートされたFootnoteを破り、アカデミー賞を受賞した。イラン国内では宿敵イスラエルを破ったと大変な興奮だったそうだ。アスガル・ファルハーディーもこれでイランの体制内でも映画を作りやすくなったかとは思うが、「どうだ、イランは俺のおかげでイスラエルに打ち勝ったんだ」とは思ってほしくない。彼はそんな人ではないと信じたい。彼のオスカー受賞のスピーチは素晴らしかったからだ。