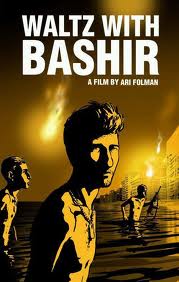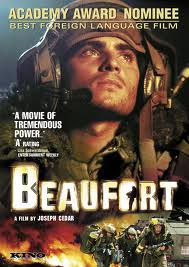この映画は『シリアの花嫁』で一躍イスラエルのトップ監督の一人に躍り出たエラン・リキルスによる製作である。
この映画は『シリアの花嫁』で一躍イスラエルのトップ監督の一人に躍り出たエラン・リキルスによる製作である。
イエルサレムにあるイスラエルの大手製パン工場で働く出稼ぎ労働者の女性が、マーケットで自爆テロのため死亡するが、縁故者がいないので引き取り手もなく死体置き場に放置されていた。一人の新聞記者がそれを嗅ぎ付け、大企業の非人道さというテーマで記事にするという。パン工場の女社長は工場の評判が落ちないように、PRとして死体を彼女の母国で埋葬することを決定し、人事部長にそれに付き添えという出張命令を出す。記事をスクープした無礼な記者もそれを確認するために同行するという。
人事部長は、妻子と別居状態で、家庭崩壊の危機にある。娘の修学旅行の運転手をして娘との交流を考えていたのにそれもおじゃんになった。人事部長は記者と共に彼女の母国に到着するが、彼の夫はもう彼女と離婚しているので、遺体を引き取る権利がないという。彼女のティーネージャーの息子はぐれてしまい、家を追い出されたて仲間と路上で暮らしている。人事部長は、息子を連れ、1000キロ離れた村に住む祖母を訪ねていくがその途中でいろいろと思いがけないハプニングが起きる。
イスラエルの映画というと、日本人にも知られている映画はとしては『戦場でワルツを』 『ボーフォート レバノンからの撤退』『アジャミ』などの政治色の強い映画と、『迷子の警察音楽隊』や『ジェリー・フィッシュ』のようなイスラエルの庶民の心を描く路線とに大別できると思うが、これは後者である。『ジェリー・フィッシュ』では、建国者であるホロコースト世代から切り離されて建国の意義がぴんとこない若い世代の鬱屈した感情を描いているが、この映画も家族や人間関係や仕事に完全に幸せでない人事部長の心理を内面から描く。また『ジェリー・フィッシュ』と同じく、イスラエル人から無視されがちな外国人労働者の生活も一つのテーマになっている。
イスラエルでの低賃金労働は元来パレスチナ人に任せられていた。しかしパレスチナ人の自爆テロの増加、そしてパレスチナ人への隔離政策でパレスチナ人の入国が次第に困難になってくると、その労働を任せるために外国人労働者を雇うようになったのである。外国人労働者への無視というか冷たい視線はイスラエルに限らずどこの国でも共通であるかもしれないが、イスラエルではパレスチナ人に対する警戒心と上から目線が、その仕事を受け継いだ外国人労働者に受け継がれているという可能性もあるのではないか。
この映画は『シリアの花嫁』でも表現されたような、エラン・リキルス独自の強い主題が前面に押し出されている。それは、「国際社会におけるイスラエル人の良心を示すこと」である。人事部長は最初は仕事で従業員の故国に行ったのだが、次第に彼女の家族と生まれた国に対する理解と心の繋がりを深めて行く。そして彼女の家族から、イスラエルが彼女の選んだ祖国なのだから、そこに彼女を葬ってほしいという言葉まで引き出してしまうのだ。また彼の娘も修学旅行の運転手なんかどうでもいいから、その女性の死体の面倒をきちんと見てあげてほしいと主張するのだ。
自爆テロの犠牲者になった彼女が生まれた国は一体どこだったのだろうか。未だに社会主義政権の名残の官僚主義や賄賂が生きている国。虚無的なストリートキッズが町の隅々に隠れている、崩れかかったような活気のない首都。東方正教を信じている人々。馬が交通手段としてまだ残っている貧しい寒村。映画はこの国の名前を明示しないが、聴衆にはそれがルーマニアであることが次第にわかってくる。なぜルーマニアなのか。
ルーマニアにもユダヤ人が多数住んでいた。彼らは他の国に住んでいるユダヤ人と同じく第二次世界大戦下でホロコーストの被害にあったが、それはポーランドやチェコで起こったホロコーストのようには知られていなかった。その理由は、そのホロコーストがドイツのナチスの手によったものではないので、ドイツの非ナチ化の告発の対象にならなかったからである。ルーマニアのユダヤ人虐殺はルーマニア人の手でなされ、その後の40年に渡る社会主義政権の下では極秘にされ、或いは否定され、ルーマニアのユダヤ人ホロコーストが公式の話題になったのは、2000年代に入ってからであった。
第二次世界大戦でのルーマニアとドイツの関係は複雑である。ルーマニアは領土を巡ってソ連と争っていたので、第二次世界大戦ではドイツ側の枢軸国として参戦したが、次第に反ドイツの態度を強め、ドイツ敗戦の気配が見え始めると1944年には連合国側に鞍替えして、当時ドイツ支配下にあったチェコに対する攻撃を始めた。ユダヤ人への迫害は1940年ころから次第に顕著になったが、当時の政権の情勢により、ユダヤ人の迫害が緩和されたり厳しくなったりというジグザグを取り、また地域によってもその状態が異なったようだ。またユダヤ人虐殺の主導をしたのは、ルーマニアの各地域の指導者、ナチス、或いはソ連と混沌とした情報があり、すべてが明らかにされてはいない。第二次世界大戦後の社会主義政権の誕生後の秘密主義で肝心な情報が消滅してしまったのかもしれない。一番知られているのは1941年に起こったオデッサの虐殺であるが、その資料も十分とはいえないようだ。
ルーマニアのユダヤ人でイスラエルに移住した人も多いが、ドイツ圏でのホロコーストが色々な資料を保存して検証されているのに対し、ルーマニアでのそれは所謂unresolved issueである。しかしエラン・リキルスによるこの映画には告発の態度はない。ルーマニアの寒村を「地の果て」といって飛び出したこの女性は、首都に移り工学学士の学位を取得しても満足せず、イスラエルで自分の人生を試そうとした。イスラエルは、そんな女性を、自国を選んでくれたのなら、あなたを受け入れますよ、という広い心を持っているということをこの映画は伝えたいのではないか。
彼の思いを一言で言えば「イスラエル人を殺すために自爆テロをする人よ。あなたはイスラエル人を殺していると思っているが、結局イスラエルに暮らしている非ユダヤ人も犠牲にしているのだ。もうこんな行為はやめようではないか。イスラエル人は戦火を止める心の準備はできているのだ」というものではないか。国際的にはイスラエル人がテロに対する警戒をなかなか解かないのが問題であると非難されることがある。しかしユダヤ人は第二次世界大戦の終結から今日まで「どうして第二次世界大戦でのナチスの動きに対抗できなかったのか」「なぜ、そんな動きに気がつかずにナチスの収容所送還の命令にやすやすと従ったのか」といつも質問される続けるのである。彼らが歴史から学んだことは、常に疑いの心を持ち慎重になれということではないのかと思うのである。