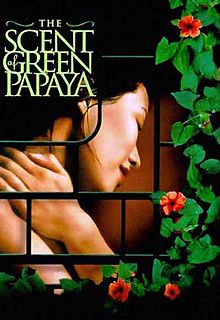 映画監督を私なりの三角形理論で分類してみると、一つの頂点にヌリ・ビルゲ・ジェイランやアンドレイ・タルコフスキーやセルゲイ・パラジャーノフのようにシネマトグラフィーの絵画性で度肝を抜いてやろうという監督がおり、もう一つの頂点にはアスガル・ファルハーディーのように巧みなストーリーの語りでしぶとく勝負をかけてくる監督がいる。三番目の頂点には、わかりやすく面白いストーリーと計算を尽くしたシネマトグラフィーを併せ持って直球で勝負してくる黒澤明やスティーブン・スピルバーグのような監督がいる。『青いパパイヤの香り』のトラン・アン・ユン監督は最初のタイプ、ビジュアル派である。
映画監督を私なりの三角形理論で分類してみると、一つの頂点にヌリ・ビルゲ・ジェイランやアンドレイ・タルコフスキーやセルゲイ・パラジャーノフのようにシネマトグラフィーの絵画性で度肝を抜いてやろうという監督がおり、もう一つの頂点にはアスガル・ファルハーディーのように巧みなストーリーの語りでしぶとく勝負をかけてくる監督がいる。三番目の頂点には、わかりやすく面白いストーリーと計算を尽くしたシネマトグラフィーを併せ持って直球で勝負してくる黒澤明やスティーブン・スピルバーグのような監督がいる。『青いパパイヤの香り』のトラン・アン・ユン監督は最初のタイプ、ビジュアル派である。
この映画には、はっきりしたストーリーは全くない。舞台は1951年のフランス支配下のベトナム。最初の三分の二は女中奉公に来た若い少女が年増の女中に、「あの人は誰?、どうなっているの?」と聞き登場人物や設定を説明するのが少しで、後はその家の少年たちが虫を殺したり、爬虫類をおもちゃにしたり、所かまわず放尿したり、物体のクローズ・アップに費やされる。残りの三分の一は突然十年後に飛び、成長した少女が他の家に女中奉公の勤め先を変え、その家の男主人に愛され、彼の妻となるシンデレラ・ストーリに変わるが、全くと言ってよいほど台詞がない。前半で稚拙なメッソドで与えられた最初の家の人間関係の情報は全くといっていいほど後半の理解には役立たない。私なりに穿って解説すると、前半は女として苦しい生活を強いられた監督の母を、奉公先の優しく忍耐強い女主人として描き、後半は自分が幸福にしてあげている若い世代を、成長した少女の姿で描くという意図なのかもしれない。成長した女中をトラン監督の妻が演じている。まあ、全くストーリーも台詞もないのだから、私のような解釈をした人などいなかもしれない。観衆に「綺麗な画面は時々あるけど、何が言いたいの」「異国情緒を利用して得している部分がありそうでずるい」と思わせる映画である。
トラン監督はサイゴン陥落の時に、両親と共に共産主義政権から逃げてフランスに移住したベトナム人である。フランスの名門の映画大学で映画を学んだから、ヌーベル・バーグの理論やアンドレイ・タルコフスキーのシネマトグラフィーの手法をそこで叩き込まれただろう。この映画は彼の卒業後の第一作で、監督はこの映画を作製したときは30歳そこそこであった。自分の作風について、この映画が大評判になった時「僕は伝統的なストーリー・テリングは完全に否定し、新しい言語、ボディ・ラングイッジで、映画を作りたいと思っています。思考的な理性に変わってボディ・ラングイッジを駆使することにより、聴衆をチャレンジし、映画のエッセンスを感じ取ってもらいたいのです。」という青臭いマニフェストを宣言している。要するに、ストーリや言語や思想や情報は映画には不必要なもので、自分は映像だけで聴衆を説得してやるんだ、ということである。20年経った今でも、トラン監督は同じ考えなのだろうか、と興味深々である。というのも、美しい映像さえ提供すれば、優れた映画作家だというのは間違っていると私は思うからだ。映画とは、思索、主張、事実、想像、感性、情報、ストーリー、演技、音声、シネマトグラフィーなど無限な要素を最適に統合した最終結果を観衆に提出するものであり、その様々な映画作成の要素の中でもストーリー性は非常に重要な地位を占めている。もし映像だけで勝負したいのなら、別のメディアを使えばよいのである。映画というメディアを表現の媒体として使用しているなら「綺麗な画像だからいいでしょう、ストーリなんてなくっても」というのは、傲慢であり怠惰であると私は思う。ヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督はその美しい映像で見る者の度肝を抜くが、彼の作品には一貫した問題意識と思想があり、美しい画像はその心象風景である。アスガル・ファルハーディー監督の画像は情報に溢れた見事なものであり、彼のストーリー性を補強している。「映像が斬新じゃないから、アスガル・ファルハーディーは才能がないね」という人は一人もいないであろう。要するに、ストーリーとシネマトグラフィーは手に手を取って相手を助けるものであり、映画ではいい画像さえあればストーリがいらないという考え方は間違っている。それなら、映画というメディアを使う必要はないのである。
トラン監督は30代前半で、カンヌやベネチアという国際映画祭で錚々たる賞を受賞している。これらの賞は、新進監督を発掘し勇気づけるという要素もあるし、国際的な映画界ではベトナム戦争から回復しているベトナムを応援しようという気持ちもあるのだろう。しかし、大学を卒業したばかりの青年が「名作」を作る前に早々と「名声」だけを得てしまったのは、幸運なことばかりとはいえないのではないか。賞を取ったということで、誰も彼の作品に厳しい批判をしてくれる人はいなくなっただろうし、人生が楽になりすぎるのは、或る意味では「呪い」でもある。彼がこの後、20年間に『ノルウェイの森』を含めて数作のみを作っている寡作監督なのも興味深い。
この映画は、男性の観衆から賞賛され、女性の観衆に嫌われる映画のような気がする。何が女性の神経を逆撫でするかというと、最初の家の女主人と成長した女中の受身的な、男性第一、男性に気に入られるのがすべてという人生態度である。女主人は主人が浮気をして全財産を持って飛び出した後姑に「息子がそうしたのは、お前に女性としての魅力が無いからだ」と言われ、もっともだと泣くだけである。女中は小さい時から憧れていた年上の男性の家に奉公先を移し、嬉々として真面目に働き、その男の婚約者から男を奪い取る。なぜ男が金持ちで上流階級の婚約者から女中に鞍替えし、愛人でなく妻としようと思ったのかには一切の説明はない。結構深刻な女性たちの人生を美しい画像だけで描こうとしても、こちらには何も伝わって来ないのだ。こういう女性は男性にとっては魅力的かもしれないが、女性の神経を逆撫でする。男の方から婚約破棄をしたのに、女に婚約指輪を返還させ、その指輪を「ふん」といった表情で自分のポケットに入れる男があざとくていやな感じである。
もう一ついけないのは、成長した少女を演じるトラン監督の妻の演技である。彼女は全く台詞をしゃべらないで、従属した女性を表現するために猫背で首をいつも45度傾けていて、下目遣いで、ねちっと体をくねらせ、唇をいつもにたりにたりさせているだけだ。いかんせん彼女が演じる映画の中の女中は不気味で不自然で不愉快である。私なりの穿った見方を言わせてもらうと、トラン監督はもちろん才色兼備の妻を愛しているから、自分の映画の主演に使いたい。しかし多分彼女は幼い頃にベトナムから亡命しているので、ベトナム語は理解できるがネイティブではないのだろう。またトラン監督にしても彼女が女優としても才能があるという確信はないのだろう。だから万が一ベトナム人の人が見てもあまりボロがでないように、彼女の台詞はゼロにしたのではないか?猫背にして体をくねらせていれば、女らしさ、従順さが出るから大丈夫だと彼が踏んでいたのなら、それは問題である。成長した女優が唯一しゃべるのは、男主人から読み書きを教えてもらって、詩の一行を短く読むくだりである。今まで映画で使われていたパパイヤは青いのだが、この時だけ彼女は黄色いアオザイを着て、子供を孕んで成熟したパパイヤのような女という感じの演技をしていたが、口を開いた彼女の表情は一転して現代っ子的な西欧的な快活さに満ちている。詩の一行を読んでいるだけなのに彼女が「はい、ぶりっ子をして、旦那様を陥落して、みごと勝ち組になりました。めでたし、めでたし」と言っているような気がしたのは私一人であろうか。
一言で言えばこの映画は、「彼と一緒にこの映画を見にいきました。彼は、見終わった後で、見事な画像だな、情緒たっぷりでこれぞ芸術、あの女優はすごい美人だったな、やはり女は従順がいい、従順な女だからこそ幸せになれるんだ、悲しいことにああいう女はもう現代では消滅してしまったな、と感激しぱなっしで、私はバ~カと思ったけど、それは口に出さないで心で笑っていました」と女性が思う映画なのではないだろうか・
