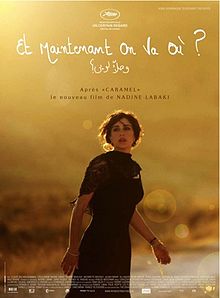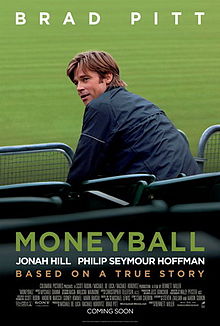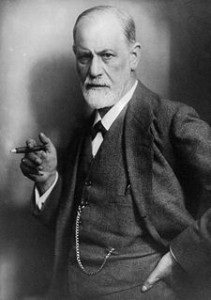トルコの世界的監督ヌリ・ビルゲ・ジェイランの最新作である。この映画の粗筋を一言で言えば、トルコの首都アンカラ地域で起きた殺人事件の証拠の死体を捜しに行く警察官、検察官、検死外科医、殺人容疑者、部下の警官と発掘作業員たちクルーが、死体放棄場所であるアナトリアで過ごした一夜とその翌日の検死を描く。
トルコの世界的監督ヌリ・ビルゲ・ジェイランの最新作である。この映画の粗筋を一言で言えば、トルコの首都アンカラ地域で起きた殺人事件の証拠の死体を捜しに行く警察官、検察官、検死外科医、殺人容疑者、部下の警官と発掘作業員たちクルーが、死体放棄場所であるアナトリアで過ごした一夜とその翌日の検死を描く。
ヌリ・ビルゲ・ジェイランの特徴がこの映画でも顕著で、特にドラマティックな展開はないが、相変わらず美しいシネマトグラフィーであり、それに惹きつけられる彼のファンの期待を裏切ることはないだろう。しかし、この映画は彼の従来の作品に比べると登場人物が多いし、一人一人のキャラクターを描写するために会話が多くなっている。またドラマティックではないにしても、従来の映画に比べたらストーリー性が強くなっていて、謎解きの要素もあるので結構長い映画なのに最後までぐっと見続けることができる。映画のテンポは観るものが一人一人の登場人物の心を消化できるように、ゆったりと進むが、それぞれの登場人物の心が複雑なので、これくらいの時間を貰えるのは却ってありがたい。また要所要所に非常に興味深いメタフォーが散りばめられている。木から落ちた林檎がころころと丘を転がり落ち、小川に落ちた後もずっと流れて行くシーンがカットなしのロングショットで映される。よくこんなシーンがとれたものだと感心してしまった。
この映画の特徴を一言で描写すれば、雨がぽつぽつ降っている水溜りに、雨粒で波紋が静かに幾つか生まれて、それが他の波紋と共鳴したり消しあったりして、いつまでも続いている、とでも言おうか。一つ一つの波紋は登場人物の心である。そして、映画を観終わったあと、聴衆の心に小さな石つぶてが静かに投げ込まれ、それがいつまでもさざなみ立っているのである。
単純な「行った、捜した、見つかった」というだけの筋なのだが、この映画の中に含まれるセンチメントは多層である。しかし私が一番強く感じたのは、「身近な女を幸福にできない男」のメランコリーであり、ニヒリズムである。
若くて結構ハンサムな外科医は離婚しており、子供もいないが、警察官はそれは却っていいことだという。こんな希望のない世界で子供を作るなんて罪だと。その警察官の子供は精神的に問題があり、それが夫婦間のいざこざになっており、彼は妻との関係に疲れきっている。検察官は全く自分の人生には問題がないという顔をして、自分が扱った面白い事件の話をしている。非常に美しい女性が子供を産んだあと、自分は死ぬと予告し、結局自分が予告したのと全く同じ日に変死したのだ。しかしその外科医はその死は自殺なのではないかと問いかける。外科医は自殺する人間の動機は他人に対する復讐なのだ、と静かに語る。その中で、観る者は、生後3ヶ月の赤ん坊を置いて自殺したのは、検察官の妻であるということを推測できるのだ。友人を殺したということで逮捕された男は、被害者と仲良く酒を飲んでいるうちについ「お前の子供は実は俺の子供だ」と口をすべらし、それがもとでの喧嘩で友人を殺してしまう。残された女は子供の実の父と育ての父を失ってしまうのだ。
この映画には女性は殆ど出てこない。唯一のキーパーソンは、警察の死体発見のクルーが夕食を取った貧しい村の村長の家で、蝋燭の光でお茶を提供した美しい娘だけである。全員が彼女のあまりの美しさに感嘆し、それぞれの人生の中で自分が不幸にしてしまった女性を思い起こすのであるが、誰も彼女に話しかける者はいない。娘が持つ蝋燭には蝿が光をもとめてぶんぶんと飛んでいる。しかし、男たちは「美しい女は不幸になるものだ」といって彼女から距離を置こうとする。
この映画は非常にクレバーな映画である。殺人事件がどこで起こったのか、聴衆は案外見過ごしてしまうのではないか。また良心的で知的で映画では肯定的に描かれている外科医が最後に下した決断は意外なものである。最後に窓から外を見やるその意思は一体何を見て、何を感じているのか。その行為に「男が遠い女に奉げる優しさ」があるのか?しかし、彼は自分に近い女に対してその優しさを奉げることができるのか。
というわけで、何ということのないストーリの中に謎かけと謎解きが混じっている、一筋縄でいかない映画なのである。この監督の映画を観るたびに、彼の映画の底に流れる虚無感は彼の性格によるものなのか、あるいは複雑な問題を抱えるトルコ社会の鬱屈さに影響されているのか、と考えてしまうのである。
トルコは地理的にも文化的にも、東西の要、ヨーロッパ文化とアジア文化の中間点である。アナトリアは小アジアとも呼ばれ、イスタンブールがギリシャや西欧文化への窓口であるとすれば、東方文化に繋がる地方でもある。ムスリムが多く、宗教心の強い地域である。チグリス川・ユーフラテス川の源流が始まる地域であり、古来から独自の文化が発達した。現在でも少数民族とされているクルド人が多数住む地域である。第一次世界大戦で破れて民族分断絶滅の危機に陥った時、民族運動の中心地になったのがアナトリアである。だからトルコの首都はこの地に近いアンカラにある。アナトリア地方は現在でも、貧しく、亜寒帯の厳しい気候を持ち、宗教的であり、風光明媚で国際的で経済的に発展しているイスタンブールとは対照的である。監督はアナトリアに対しての特別な気持ちがあるのだろうが、それは私にはわからないことである。
 アナトリアはカッパドキアなどの世界遺産である奇観で知られるが、監督はその岩がごつごつした風景は避けて、草原がゆるゆるとどこまでも続き、道がくねくねと曲がり延びて行くようなロケ地を捜したという。この映画はそんな、どこまでもうねっている草原のような映画である。
アナトリアはカッパドキアなどの世界遺産である奇観で知られるが、監督はその岩がごつごつした風景は避けて、草原がゆるゆるとどこまでも続き、道がくねくねと曲がり延びて行くようなロケ地を捜したという。この映画はそんな、どこまでもうねっている草原のような映画である。