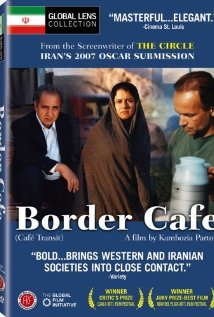1914年、クリスマス前夜フランス北部の塹壕で、フランス・スコットランド連合軍は旧フランス領を占拠し進撃して来たドイツ軍と、狭いノーマンズランドを挟んでで対峙していた。ドイツ軍に徴兵されその陣にいた国際的なオペラ歌手ニコラス・スプリンクを恋人のソプラノ歌手アナ(ダイアン・クルーガー)が訪ねてくる。クリスマス前夜、衛生兵としてスコットランドに奉仕していたパーマー神父がスコットランド陣営でバグパイプでクリスマスの曲を奏でると、ドイツ陣営のニコラスもクリスマス聖歌を歌い始める。フランス・スコットランド連合軍は思わず拍手を送り、ニコラスは中立地帯のノーマンズランドに立ち歌い続けた。それがきっかけになり、三国の将校は中立地帯で面会し、クリスマスイヴだけは戦闘を中止することを決定する。パーマー神父がクリスマスミサを行い、アナが聖歌を歌った。翌日も彼らは戦争を停止し、中立地帯に放棄された同胞の死体を埋葬し、サッカーを楽しみ、チョコレートとシャンペーンを分け合い、家族の写真を見せ合う。しかし、つかの間の友情を交換した彼らにも、戦いを開始しなければいけない時が来る。この友情の交流を知ったそれぞれの軍部や教会の上層部は怒り、友情を交わした兵士たちはその行為に対する厳しい結果を受け止めなければならなかった。
1914年、クリスマス前夜フランス北部の塹壕で、フランス・スコットランド連合軍は旧フランス領を占拠し進撃して来たドイツ軍と、狭いノーマンズランドを挟んでで対峙していた。ドイツ軍に徴兵されその陣にいた国際的なオペラ歌手ニコラス・スプリンクを恋人のソプラノ歌手アナ(ダイアン・クルーガー)が訪ねてくる。クリスマス前夜、衛生兵としてスコットランドに奉仕していたパーマー神父がスコットランド陣営でバグパイプでクリスマスの曲を奏でると、ドイツ陣営のニコラスもクリスマス聖歌を歌い始める。フランス・スコットランド連合軍は思わず拍手を送り、ニコラスは中立地帯のノーマンズランドに立ち歌い続けた。それがきっかけになり、三国の将校は中立地帯で面会し、クリスマスイヴだけは戦闘を中止することを決定する。パーマー神父がクリスマスミサを行い、アナが聖歌を歌った。翌日も彼らは戦争を停止し、中立地帯に放棄された同胞の死体を埋葬し、サッカーを楽しみ、チョコレートとシャンペーンを分け合い、家族の写真を見せ合う。しかし、つかの間の友情を交換した彼らにも、戦いを開始しなければいけない時が来る。この友情の交流を知ったそれぞれの軍部や教会の上層部は怒り、友情を交わした兵士たちはその行為に対する厳しい結果を受け止めなければならなかった。
戦争中に敵国兵が友情を交わしたというのは本当に起こったのかと思われるかもしれないが、この映画は実際に起こった事実をいろいろ繋ぎ合わせて製作されたという。クリスマス休戦や敵国間での友情の交流は第一次世界大戦の公式の記録に残っていない。しかし西部戦線で生き残った兵士が帰還後、家族や友人に口承や写真で事実を伝えたのである。
1914年に実在のドイツのテノール歌手、ヴァルター・キルヒホフがドイツ軍に慰問に行き、塹壕で歌っていたところ、ノーマンズランドの反対側にいたフランス軍の将校がかつてパリ・オペラ座で聞いた彼の歌声と気付いて、拍手を送ったので、ヴァルターが思わず中立地帯のノーマンズランドを横切り、賞賛者のもとに挨拶に駈け寄ったことは事実であるし、独仏両軍から可愛がられていたネコが仏軍に逮捕されたことも事実である。このネコは後にスパイとして処刑されたそうだ。また敵軍の間でサッカーやゲームを楽しんだことも事実であるらしい。
このクリスマス停戦は第一次世界大戦が始まった直後のクリスマスに起こっている。第一次世界大戦は史上初の総力戦による世界大戦であり、誰もがその戦いがどういう方向に発展して行くか予想もつかず、最初は戦争はすぐ終わるという楽天的な気持ちが強かったようだ。しかし戦争が長引くにつれて危険な武器や毒ガスが使用され、また最初はのんびりした偵察のために使用されていた飛行機が恐ろしい戦闘機に変化していった。戦争が激しく残酷になるにつれてこの映画に描かれているようなクリスマス停戦が行われることは稀になっていったという。
 彼らを瞬間的にでも結びつけたのは、音楽とスポーツ、そして宗教の力である。戦闘国の独仏英はみなキリスト教国で、この頃は人々の信仰も強く、クリスマスが本当に大切なものであったということも、クリスマス休戦の動機になっていたであろう。同じキリスト教国の国であるということで、敵国も理解しやすかったのであろう。もしこれがイスラム教徒とキリスト教徒、或いはイスラム教徒とユダヤ教徒との間の戦争であったなら、クリスマス休戦などは起こらなかったであろう。
彼らを瞬間的にでも結びつけたのは、音楽とスポーツ、そして宗教の力である。戦闘国の独仏英はみなキリスト教国で、この頃は人々の信仰も強く、クリスマスが本当に大切なものであったということも、クリスマス休戦の動機になっていたであろう。同じキリスト教国の国であるということで、敵国も理解しやすかったのであろう。もしこれがイスラム教徒とキリスト教徒、或いはイスラム教徒とユダヤ教徒との間の戦争であったなら、クリスマス休戦などは起こらなかったであろう。
第一次世界大戦で一番大きな政治的な変動を遂げたのはドイツである。当時ドイツはまだ帝国であり、臣民はドイツ皇帝兼プロイセン王ヴィルヘルム2世の名の下に戦ったのである。しかし大戦が続く中で国民の厭戦気分は高まり、1918年11月3日のキール軍港の水兵の反乱に端を発した大衆的蜂起からドイツ革命が勃発し、ヴィルヘルム2世はオランダに亡命し、これにより、第一次世界大戦は終結し、ドイツでは議会制民主主義を旨とするヴァイマル共和国が樹立された。
その後もドイツの政権は安定せず、敗戦後は戦勝国側からの経済的報復を受けドイツ国民は悲惨な生活を送っていた。その不満の中で1920年にナチスが結成され、それが第二次世界大戦に繋がっていくのである。映画の中では、ドイツ軍を率いたホルストマイヤー中尉はユダヤ人であった。クリスマス停戦を知った西部戦線の最高司令官であったヴィルヘルム皇太子は激怒し、ホルストマイヤー中尉の部隊を危険な東部戦線に送ってしまうが、その際にヴィルヘルム皇太子は中尉の胸にあるドイツ軍の鉄十字を自分の剣で突き「貴様は鉄十字に値しない」と怒鳴るが、それは20年後にドイツ市民権を剥奪され、ドイツ兵にも志願できず強制収容所に送られるユダヤ人の運命を暗示しているシーンであった。
この映画のメッセージを一言でいえば、「戦意は国家指導者によって形成されるものである」ということではないだろうか。この映画は英独仏の小学生が周辺の国に対する戦意を学校で愛国教育として叩き込まれるシーンから始まる。国民は敵国の兵士は顔のない獣だと思わされているから、戦争で戦えるのである。しかしクリスマスイブの夜の交流によって、初めて相手を人間と認識した兵士たちにとって、殺し合いは難しいものとなる。フランス軍を率いるオードゥベール中尉が、クリスマス停戦への非難を受けた時「ドイツ人を殺せと叫ぶ連中よりも、ドイツ兵の方がよほど人間的だ!」と反論する。また戦争に戻らなければならない兵士の「我々は(今日だけでも)戦争を忘れることができる。でも戦争は我々を忘れはしない」という言葉がいつまでも聴衆の心にのこるだろう。
 この映画は美しい細部の描写が印象的な佳品なのだが、もし私が難点をつけるとしたら、オペラ歌手を演じたダイアン・クルーガーのあまりにも明らかな口パクだろう。彼女が兵士の前で歌う聖歌がこの映画の大きな転換点になるはずなのだが、歌っている彼女の体の震えもないし、口も平板にパクパクさせているだけで、素人目にも歌詞と彼女の口の動きが外れているのが明らかな瞬間が多すぎるのだ。美しい絵のような彼女の口だけがパクパクと切れたように動いているので、ここで映画の感動から冷めた聴衆も案外多いのではないか。ダイアン・クルーガーは確かに美しいがこの映画では本物のオペラ歌手、たとえばこの映画で実際に歌声を提供しているナタリー・デセイなどに任せた方がよかったのではないか。聴衆はダイアン・クルーガーの口パクより、むしろスコットランド軍のパーマー神父が奏でるバグパイプの演奏に感動するのではないか。『ムッソリーニとお茶を』でも、映画はナチスに占領されたイタリアの町を解放したスコットランド軍がバグパイプを弾きながら町に入ってくるところで終わる。バグパイプの音はなぜあれほど明るくて、楽天的で、悲しくて、感動的なのであろうか。
この映画は美しい細部の描写が印象的な佳品なのだが、もし私が難点をつけるとしたら、オペラ歌手を演じたダイアン・クルーガーのあまりにも明らかな口パクだろう。彼女が兵士の前で歌う聖歌がこの映画の大きな転換点になるはずなのだが、歌っている彼女の体の震えもないし、口も平板にパクパクさせているだけで、素人目にも歌詞と彼女の口の動きが外れているのが明らかな瞬間が多すぎるのだ。美しい絵のような彼女の口だけがパクパクと切れたように動いているので、ここで映画の感動から冷めた聴衆も案外多いのではないか。ダイアン・クルーガーは確かに美しいがこの映画では本物のオペラ歌手、たとえばこの映画で実際に歌声を提供しているナタリー・デセイなどに任せた方がよかったのではないか。聴衆はダイアン・クルーガーの口パクより、むしろスコットランド軍のパーマー神父が奏でるバグパイプの演奏に感動するのではないか。『ムッソリーニとお茶を』でも、映画はナチスに占領されたイタリアの町を解放したスコットランド軍がバグパイプを弾きながら町に入ってくるところで終わる。バグパイプの音はなぜあれほど明るくて、楽天的で、悲しくて、感動的なのであろうか。