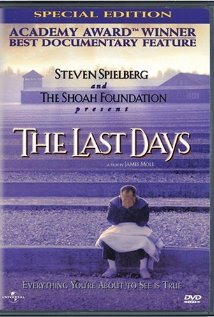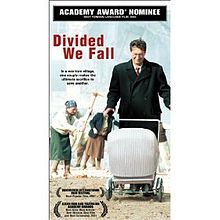ミヒャエル・ハネケ監督の作品といえば、『ファニーゲーム』や『ピアニスト』のように、不愉快な登場人物が次から次へと恐ろしい行為を繰り返し、見続けるのは恐ろしいが、きっと何か最後に説明がありすっきりさせてくれるだろうと聴衆に期待させ、結局何も説明がなく、聴衆は心が切り刻まれたまま放り投げられるというパターンが多い。アメリカ映画を好む聴衆からは「許されない」映画なのだが、彼の作品はすべてカンヌ映画祭を始めとするヨーロッパ映画祭で最高賞を受賞しているのだから、それなりにヨーロッパ映画に見慣れた聴衆の心を深くつかむのだろう。
ミヒャエル・ハネケ監督の作品といえば、『ファニーゲーム』や『ピアニスト』のように、不愉快な登場人物が次から次へと恐ろしい行為を繰り返し、見続けるのは恐ろしいが、きっと何か最後に説明がありすっきりさせてくれるだろうと聴衆に期待させ、結局何も説明がなく、聴衆は心が切り刻まれたまま放り投げられるというパターンが多い。アメリカ映画を好む聴衆からは「許されない」映画なのだが、彼の作品はすべてカンヌ映画祭を始めとするヨーロッパ映画祭で最高賞を受賞しているのだから、それなりにヨーロッパ映画に見慣れた聴衆の心を深くつかむのだろう。
『白いリボン』はミヒャエル・ハネケの作品の中では、比較的に一般受けがする映画なのではないだろうか。モノクロだが非常に美しく、1913年の北ドイツの小村の精髄を忠実に再現したシネマトグラフィー、美男美女は一人も出てこないが、子役を含めて実在感のある俳優たちの好演、そして謎解きを含んだ魅力的なストーリーが見る者の心を最後まで引っ張っていく。しかし、これは探偵ドラマではないし、犯人が最後まで明らかにされないのは、いつも通り「ハネケ的」である。
この映画は1913年に起こった村の医師の不審な落馬事故で始まり、1914年に第一次世界大戦の勃発時と同時に起こった医師の家族と隣家の助産婦の親子の不審な失踪で終わる。登場する家族は、村の半分の人口を雇用する勢力者の男爵家、牧師の家族、医師一家と医師と性的関係のある助産婦とその幼い息子、男爵に仕える執事の一家、男爵家の小作人の一家、そして村の学校の教師とその恋人のエヴァである。
医師と助産婦の一家に起こる事件は、不審な落馬事件、医師の助産婦に対する侮蔑と別れ話、医師の14歳の娘に対する性的な関係、助産婦の知恵遅れの子供に対する暴行事件、そして医師と助産婦一家の突然の蒸発である。
男爵家に起こるのは、領土内での小作人の妻の事故死、小作人の息子によってキャベツ畑を荒らされたこと、幼い息子の誘拐暴行事件、その息子の溺死未遂、納屋の火災である。
小作人の一家に起こるのは妻の事故死、息子の報復による男爵家のキャベツ畑の狼藉、男爵家の仕事をクビになった父の自殺である。
執事の家に起こるのは、新生児の部屋の窓が開け放されて赤ん坊が死にかかること、執事の子供による男爵家の幼い息子の溺死未遂事件である。
牧師の家では子供の些細な失敗に対しても厳格な体罰が行われ、牧師である父は思春期に差しかかった長女と長男に「純潔」の心を保つために白いリボンを巻きつける。牧師はこれは親の愛の表れであるというが、あまりにも厳しく友人の前で叱責された長女は失神してしまい、その後父親の可愛がっている鳥を殺してしまう。また長男も自殺に近い不審な行為を行う。
教師は他の町の出身で、やはりその町の隣町から男爵家に乳母として出稼ぎに来ている若いエヴァと知り合い結婚を申し込む。教師は次から次へと起こる事件の背後には牧師の長男と長女が関係しているのではないかと疑い牧師に話しに行くが、逆に牧師から名誉毀損だと脅かされてしまう。
映画を一見すると、教師が疑ったように、欺瞞的な牧師の親から抑圧された長男と長女が次々と事件を起こしていくように見えるが、それは方向の違う解釈のような気がする。犯人がはっきりしているのは、小作人の息子が母親の仇をとるためにキャベツ畑を荒らすこと、執事の息子が男爵の息子を突然川に突き落とすこと、牧師の長女が牧師の鳥を殺すことだけである。それ以外は単に事故かもしれないし、映画に出てくる家族以外の村人たちが男爵を憎んでやったことかもしれない。よく考えると10歳前後の子供たちが、夜放火したり、他人の家に入り込んだり、針金を木に精巧に結んで馬の通り道を防いだり、自分の顔を知っている男爵家や助産婦の息子を誘拐して暴行したりするのは難しいと思われるし、子供たちがすべての事件のマスターマインドである方が非現実的ではないだろうか。しかし、未解決の事件が重なることで村人たちの間で不信感が募っていくとか、子供たちの間で犯罪に対する好奇心が強まっていくのは事実である。
この映画は、村を支配している2つの勢力が次第に勢力を失っていく過程を描いている。一つは男爵に代表される政治的支配者である。男爵はその土地を所有しているが、次第に貨幣経済制の浸透という近現代社会への発展で金策に苦労しているようだし、貴族階級による支配に対する反抗の気持ちも小作人に芽生えている。社会主義思想、労働者の権利思想がひたひたとこの田舎村にも押し寄せているのだ。そして、貴族制を支えていたドイツ帝国も第一次世界大戦の敗北で崩壊してしまうのである。
もう一つはプロテスタントの禁欲主義が畸形化し、牧師は人々の心も救えないし、自分の子供の心さえ蝕んでいるということである。私は牧師の長女長男は犯罪の殆どには加担していないと思うが、彼らは父の与える体罰や「愛しているからこそ、罰する」という偽善的な言葉を疑い始めている。まだ子供だから何もできないが5年後には親の存在そのものを否定する人間になりかねない。そんな怖さをこの映画は描いている。
言葉を変えれば、支配者階級とそれに反抗する階級、偽善的な牧師の権威とそれに反抗する子供たち、専制的な男とそれに従属する女たちの対立の構図である。
ヒトラーは1889年生まれだから、第一次世界大戦が始まった時は25歳であり、この映画に出てくる子供たちより若干年長である。つまりこの映画に出てくる子供たちは、第二次世界大戦でヒトラーを賛美しナチスを支持した世代なのである。この映画はナチスの勃興を説明してはいない。しかしこの映画の中で望遠鏡を覗けばその地平線の果てにナチスが見えてくるような映画なのである。しかしハネケはそれについて何も語っていない。
というわけで、聴衆は『白いリボン』を見た後で、取り残されたような悔しさ、もどかしさを感じるのだが、これではずばりハネケの罠に嵌ったことになる。彼は彼自身の映画を「私の映画は、安易に回答を与え聴衆の疑う力を失わせてしまうアメリカ映画に対する抵抗であり、批判なのです。私の映画は聴衆に即座の(そして往々にして誤っている)回答を与える代わりに、頑固なまでに質問を繰り返します。映画を開放して終わるのではなく、まだ真実には距離があるということを聴衆に確認したいのです。そして映画で聴衆がみな同意して満足するのではなくて、まだ終わっていないということを聴衆の心に波立てたいのです」という風に説明している。
このハネケの難解な言葉を私なりに解釈させてもらえば「この映画の中の15個の謎を解こうとして犯人探しをして下さって苦労様と言いたいんですが、残念ならが答えは間違っています。というか、誰もが同意する真犯人などはいません。私はあなたの頭を使って考えてもらいたいからこの映画を作ったのであり、答えは用意していません」ということなのだろうか。