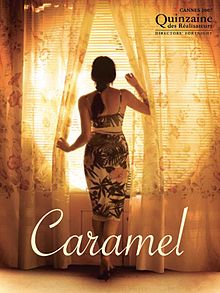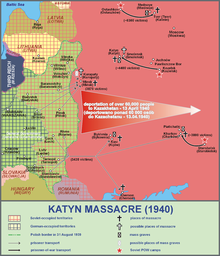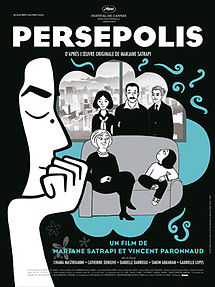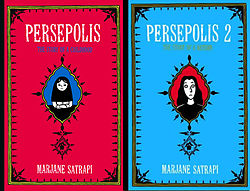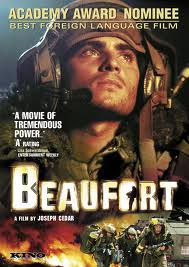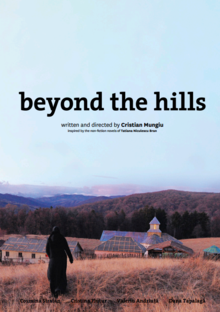 2000年代に入ってからのルーマニア映画の活況は非常に目覚しい。毎年、何らかの映画が国際映画祭の最高賞を受賞しており、これらの動きはルーマニアのニューウェーブと言われている。今年はついにクリスティアン・ムンギウによる『汚れなき祈り“Dupa dealuri(Beyond the Hills)”』がアカデミー賞外国語映画賞部門でのショートリストにまで残り、最終候補ノミネーションにあと一歩まで来ている。もしノミネートされれば、ルーマニア映画界で初の快挙となるだろう。ルーマニアのニューウェーブというのは、2000年代から始まった国際的に注目され続けるルーマニア映画の総称に過ぎないが、社会性が強く、素人っぽくミニマリストの写実性という手法を取るということでは、ある種の共通性がある。社会主義の崩壊時に10代20代だった世代が今30代40代となり、西欧やアメリカの映画技術に影響され、新しい映画を作っている。
2000年代に入ってからのルーマニア映画の活況は非常に目覚しい。毎年、何らかの映画が国際映画祭の最高賞を受賞しており、これらの動きはルーマニアのニューウェーブと言われている。今年はついにクリスティアン・ムンギウによる『汚れなき祈り“Dupa dealuri(Beyond the Hills)”』がアカデミー賞外国語映画賞部門でのショートリストにまで残り、最終候補ノミネーションにあと一歩まで来ている。もしノミネートされれば、ルーマニア映画界で初の快挙となるだろう。ルーマニアのニューウェーブというのは、2000年代から始まった国際的に注目され続けるルーマニア映画の総称に過ぎないが、社会性が強く、素人っぽくミニマリストの写実性という手法を取るということでは、ある種の共通性がある。社会主義の崩壊時に10代20代だった世代が今30代40代となり、西欧やアメリカの映画技術に影響され、新しい映画を作っている。
ルーマニアの映画は社会主義体制でほぼ壊滅してしまったので、若い世代である彼らの頭を抑える重鎮とか先輩の監督はいないので、彼らは比較的自由に活動ができる。彼らは感受性の強い十代で天地が引っ繰り返るような社会変化を経験し、その後の国家の再建の困難さも目撃しているので、表現したい題材には事欠かない。また全世界的に「今、ルーマニアの人々は何を感じ、考えているのか」という好奇心もあり、ルーマニアの映画に耳をすませている聴衆もいる。西欧の映画に関する情報もどんどん入ってくるし、EU加入後移動の自由も保証された。また世界的規模での名声を得た隣国トルコのヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督のようなロール・モデルも身近にいる。映画製作に対するすべての条件が熟してきたのだ。ルーマニアの映画がカンヌやベルリンの映画祭で大きな賞を受賞するたびに「国の名誉だ」という喜びの声が国内で沸き起こる。まるで、かつてオリンピックの体操競技で選手が金メダルを獲得した時のように。
 『4ヶ月、3週と2日』は、ルーマニアのニューウェーブの中では国際的に最も成功した映画である。チャウシェスク大統領による独裁政権のルーマニアを舞台に、妊娠をしたルームメイトの違法中絶を手助けするヒロインの一日を描く。監督は『汚れなき祈り』で、2013年のアカデミー賞ノミネートに王手をかけているクリスティアン・ムンギウである。クリスティアン・ムンギウは1968年生まれであるから、まだ44歳であるが、経歴を考慮に入れるとルーマニアで最も成功している監督の一人だといえるだろう。
『4ヶ月、3週と2日』は、ルーマニアのニューウェーブの中では国際的に最も成功した映画である。チャウシェスク大統領による独裁政権のルーマニアを舞台に、妊娠をしたルームメイトの違法中絶を手助けするヒロインの一日を描く。監督は『汚れなき祈り』で、2013年のアカデミー賞ノミネートに王手をかけているクリスティアン・ムンギウである。クリスティアン・ムンギウは1968年生まれであるから、まだ44歳であるが、経歴を考慮に入れるとルーマニアで最も成功している監督の一人だといえるだろう。
社会主義政権下のルーマニアでは人工妊娠中絶は非合法であった。ルーマニアの若いカップルは多くても2~3人くらいしか子供をほしがらず、人口減少を恐れたチャウシェスク大統領は1968年に、人工妊娠中絶を法律で禁止としたからである。その結果、非合法に危険を冒して秘密裏に妊娠中絶を行って死亡する女性もいた。『4ヶ月、3週と2日』はエリートであるはずの大学生の主人公が、ルームメートの中絶を助けるために飛び回る様子が描かれる。その友達が妊娠した理由やその相手は一切描かれず、親にも相談せず違法の医師を友人の口コミで捜して行く現実、荒涼とした通りを野良犬が歩き回る首都ブカレストの様子、タバコを現金代わりに持ち歩く主人公、質素なアパートの中に一歩入ると密かに贅沢を楽しんでいる(どうやら金持ちらしい)主人公の恋人の家族、もし主人公が妊娠したらどうしようかと真面目に考えていない主人公の恋人など、社会主義政権崩壊の直前のブカレストの知識人の生活も垣間見える。
 『俺の笛を聞け』は新人フローリン・セルバンの監督、ベテランのカタリン・ミツレスクの脚色、プロデュースによる映画で2010年のベルリン映画祭において銀熊賞(審査員グランプリ)とアルフレッド・バウアー賞の2冠に輝いてる。カタリン・ミツレスクは1972年生まれなのでまだ40歳である。2004年に作成した『トラフィック』がカンヌで短編映画大賞を受賞し、この映画がルーマニアのニューウェーブの隆盛のきっかけになったといわれる。2006年の『The Way I Spent the End of the World』が国際的に大きな注目を浴びた。監督のフローリン・セルバンは1975年生まれ、アメリカを中心に活躍している。
『俺の笛を聞け』は新人フローリン・セルバンの監督、ベテランのカタリン・ミツレスクの脚色、プロデュースによる映画で2010年のベルリン映画祭において銀熊賞(審査員グランプリ)とアルフレッド・バウアー賞の2冠に輝いてる。カタリン・ミツレスクは1972年生まれなのでまだ40歳である。2004年に作成した『トラフィック』がカンヌで短編映画大賞を受賞し、この映画がルーマニアのニューウェーブの隆盛のきっかけになったといわれる。2006年の『The Way I Spent the End of the World』が国際的に大きな注目を浴びた。監督のフローリン・セルバンは1975年生まれ、アメリカを中心に活躍している。
『俺の笛を聞け』は非行少年更生施設に収容されている18歳の少年が主人公である。なぜ彼がここに収容されなければいけなかったのかに関する説明は一切ない。しかし、ルーマニアの人々は大人の育児放棄によって孤児院に引き取られる子供がチャウシェスク政権下ではたくさんいたということを知っている。これらの子供たちは「チャウシェスクの落とし子」と呼ばれ、ストリートチルドレン化するなど、後々までルーマニアの深刻な社会問題となった。また、社会主義政権の崩壊後、現金収入を得るために自分の子供をルーマニアにおいてイタリアやスペインなどに出稼ぎに行く親が増えた。残された子供たちは何らかの手段で生きていかなくてはならず、そういった子供たちが犯罪を犯し、この映画の主人公のように少年刑務所に送られてきたのであろう。
『俺の笛を聞け』はハンドカメラを使い長いショットを取る。だから映像がぶれて、何となく素人が取ったドキュメンタリーのような印象を与える。フローリン・セルバンはアメリカの大学で映画学を専攻しているから、洗練された映画はたくさん観ているだろうし、作ろうと思ったらそれなりに洗練された映画を作れるだろうが、敢えてこういった素人的な、素材を生でぶつける手法を選んでいるように思われる。
ルーマニアには職業俳優もあまりいない。これらの映画に出演しているのは、全国的オーディションで選ばれた素人や、数少ない映画大学の学生たちである。しかし、中年にさしかかろうとしているカタリン・ミツレスクやクリスティアン・ムンギウによる俳優や映画人養成も始まるだろうし、ルーマニアのニューウェーブに新しい成熟が始まるのも時間の問題だと思われる。