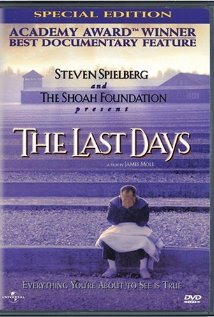『太陽の雫』は、19世紀のオーストリア=ハンガリー帝国時代から1956年のハンガリー動乱までのハンガリーの歴史を、5世代に渡る、あるユダヤ人一家を中心に描く歴史大河ドラマである。
『太陽の雫』は、19世紀のオーストリア=ハンガリー帝国時代から1956年のハンガリー動乱までのハンガリーの歴史を、5世代に渡る、あるユダヤ人一家を中心に描く歴史大河ドラマである。
この映画の魅力は、ハンガリーの歴史をわかりやすく描いていることである。一家の第一世代はオーストリア=ハンガリー二重帝国の田舎の村の居酒屋のオーナー。彼が若くして死んだあと長男(第二世代)がブタベストの工場に出稼ぎに出て、家伝の薬草酒のレシピを用いた酒メーカーのオーナーとして大成功する。その息子(第三世代)は法学者となり、ユダヤ系の苗字をハンガリー風の苗字に変え、皇帝に忠実な裁判官となる。しかし、ハンガリーが第一次世界大戦で敗北したあとハンガリー・ソビエト共和国が誕生すると、彼は戦犯として自宅監禁になり失意のうちに世を去る。
ハンガリー・ソビエト共和国はルーマニアの介入で打倒され、王政が復古するが、第一次世界大戦や、その後のハンガリーの共産党を打倒したルーマニアにより、国土の大半を失ったハンガリーは苦い思いでナチス政権に近づいて行く。第二次世界大戦では失地回復のため、枢軸国に加わったハンガリーも、1944年に枢軸国からの離脱を望むようになるが、ナチスドイツ軍に阻止されてしまう。第四世代は、フェンシングのナショナル・チャンピオンになり、ベルリンオリンピックの金メダリストにもなる。彼は1936年のベルリン・オリンピックに出場資格を得るためにカトリックに改宗した。しかし彼は結局強制収容所に送られて殺害されてしまうのだが。
命からがら強制収容所から戻って来た第五世代はソビエト連邦の後押しで成立したハンガリー人民共和国で秘密警察に参加し、ナチスに加担した人間の告発を始める。しかし、彼の仕事は次第に反スターリン派の愛国者を告発することに変質していく。1956年のハンガリー動乱の勃発で反ソビエト連邦軍の演説をした彼は逮捕され投獄された。釈放して家に戻った彼は今や一家の唯一の生き残りであった。彼は自分の苗字を再び元のユダヤ系の苗字に戻し、ユダヤ人として生きて行こうと誓う。
この映画でもう一つ面白いのは、なぜハンガリーのユダヤ人がひたひたと押し寄せるナチスの反ユダヤ主義を感じつつも、逃げずにハンガリーに留まったかをうまく説明していることである。反ユダヤ主義は裕福で社会的地位の高かったユダヤ人の特権を部分的に抑圧する法改正で始まったが、第一次世界大戦で皇帝のために戦った兵士とその家族にはその法は適用されなかった。また国威高揚に貢献した者、例えばオリンピックのメダリスト等もその例外の対象となった。つまりこの一家には反ユダヤ法は適用されなかったのだ。そんな状況で、すべての財産を捨てて言葉もわからない異国に逃亡しなければならない理由はなかった。しかし、この映画は、なぜ結局すべてのユダヤ人が強制収容所に送られてしまうようになってしまったのかについては、一言も説明していないが。
壮大なテーマを描いた力作であるにも拘わらず、この映画は名作或いは偉大な映画とはみなされないような気がする。なぜこの映画が名作になれなかったのかを、私なりに考えてみたい。
まず最初の理由は、第三、四、五世代(この三人はすべて英国の俳優レイフ・ファインズによって演じられている)の主人公の描かれ方である。この三人は権力志向、上昇志向が強くて、それを得るためには苗字を変えたり、宗教を変えたりという努力をする。しかし、女性に対する愛はあまり無い男たちである。女性からの熱烈なアタックで、「だめ、だめ」と言いつつも結局情欲におぼれてしまい関係を持つが、最後にはその女性の誘惑を「お前のせいで、自分の人生が破壊された」と冷たく非難する男である。彼らが相手にした女性も、自分の妹として育てられた女性(第三世代)、自分の兄の妻(第四世代)、自分の上司である冷徹なスターリン主義者の妻(第五世代)とすべて背徳というか危険な匂いが漂う関係である。女性が好きな男性のタイプは「実力はあるが、権力べったりではなく、女性を心から愛し、その愛を貫く」というものであろう。この映画の主人公はすべてその逆を行き、背徳とか、肉体だけの関係などという女性の最も嫌いな匂いをぷんぷんさせているので、女性の感情を逆撫でするのは無理もなかろう。しかし、映画の聴衆の50%は女性なのであるから、女性の支持を失ったらこわいのである。
この人物描写は、ホロコーストという重いテーマを描く映画としては、かなり危険なやり方である。下手をすれば、「なるほど、ホロコーストが実際にあった事実ということは認めましょう。でも、それを起こした際には、ユダヤ人にも責任があったのではないのですか?」という非常に危険な議論を起こしかねないのである。もちろん、誰だって完璧無欠の聖人君子であるはずはない。しかし、これだけの重いテーマを描くのなら、それなりの注意深さも要求されるのではないだろうか。
この映画の作者であり監督でもあるのは「メフィスト」でアカデミー外国語賞を受賞するなど、ハンガリーを代表する映画人である、サボー・イシュトヴァーンである。彼については2006年に、1956年のハンガリー動乱の後にスパイとして、仲間の監督や俳優に関するレポートを書いていたことが報道された。彼は最初はそれを否定していたが、結局後にそれを事実として認めることになるのだが、彼の周囲には彼を擁護する人が多かったという。ハンガリー動乱の後の異様な政治的締め付けを受け、警察国家となったハンガリーで生き延びることは容易でなかったに違いない。そういう残酷な時代だったのである。
もう一つの理由は、この映画は五世代の一家の流れを3時間で追う大河ドラマなので、個人の描写が表層的になり、事件の一つ一つが継ぎはぎな印象を受けることである。しかし、そのモデルになった人々は非常に魅力的である。
ハンガリーがフェンシングに強く、その金メダリストの中にユダヤ人がいたのは事実である。アッティラ・ペッチョーは1928年のアムステルダムオリンピックと1932年のロサンジェルスオリンピックでサーベルの団体戦で優勝している。アンドレ・カボスは1932年のロサンジェルスオリンピックではサーベルの団体戦で、1936年のベルリン・オリンピックではサーベルの個人戦と団体戦両方で金メダルを獲得している。二人ともナチス政権化で強制収用所に送られて死亡している。この映画の第四世代の男は、アンドレ・カボスがベルリンオリンピックの個人戦で優勝したことと、アッティラ・ペッチョーが収容所で同胞のハンガリー人に非常に残酷な手法で処刑されたことを基にして描かれているように思われる。
また第五世代の男の上司は実在の人物ライク・ラースローをモデルにしている。彼はユダヤ人の共産党主義者で、アウシュビッツから奇跡的に生還し母国ハンガリーの復興に全力をつくしたが、スターリン主義者に嫌われ1949年に処刑された。その後、ハンガリー動乱で一時名誉回復されたが、その後ハンガリーは動乱の鎮圧と共に警察国家として暗黒期に移行していくのである。