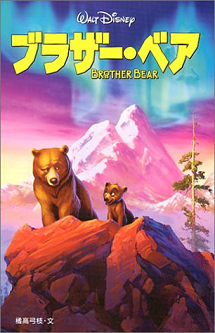Category Archives: 2003
[映画] みなさん、さようなら Les Invasions barbares The Barbarian Invasions (2003年)
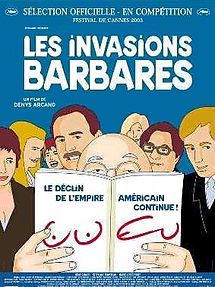 1986年に『アメリカ帝国の滅亡』を作成して17年経った2003年に、 ドゥニ・アルカン監督はその続編として『みなさん、さようなら』を作成した。ドミニク学部長を中心として展開した 『アメリカ帝国の滅亡』と異なり、『みなさん、さようなら』ではレミとルイーズの人生に焦点が当たっているが、中心人物は、レミとルイーズの息子セバスチャンとダイアンの娘ナタリーである。
1986年に『アメリカ帝国の滅亡』を作成して17年経った2003年に、 ドゥニ・アルカン監督はその続編として『みなさん、さようなら』を作成した。ドミニク学部長を中心として展開した 『アメリカ帝国の滅亡』と異なり、『みなさん、さようなら』ではレミとルイーズの人生に焦点が当たっているが、中心人物は、レミとルイーズの息子セバスチャンとダイアンの娘ナタリーである。
ロンドンで投資家としてばりばり稼いでいるセバスチャンは、父親レミが癌を患っているとの知らせを聞き、婚約者のガエルを連れて故郷のモントリオールに戻った。父母は離婚して、セバスチャンはあまり父と暮らした思い出はなかったが、母に頼まれ、父親の最期の日々を楽しいものにしようと決心する。
 労働組合に支配されている病院は能率が悪く、病室はたくさん空いているのに患者たちは廊下に置かれている。セバスチャンは金の力に物を言わせてレミの個室を確保すると、父の昔の同僚のダイアン、ドミニク、ピエールとクロードを招き、その個室は同窓会兼パーティーのような趣になる。あれだけ結婚をバカにしていたピエールは若い妻と結婚して、小さいわが子の育児に精を出す毎日で、それが本当に楽しそうである。男性遍歴を重ねていたゲイのクロードも、パートナーと安定した生活を送っているようだ。セバスチャンは大学の学生を買収して、病院に来させ、如何にレミが優れた教師であったかという芝居をさせてレミを喜ばせる。
労働組合に支配されている病院は能率が悪く、病室はたくさん空いているのに患者たちは廊下に置かれている。セバスチャンは金の力に物を言わせてレミの個室を確保すると、父の昔の同僚のダイアン、ドミニク、ピエールとクロードを招き、その個室は同窓会兼パーティーのような趣になる。あれだけ結婚をバカにしていたピエールは若い妻と結婚して、小さいわが子の育児に精を出す毎日で、それが本当に楽しそうである。男性遍歴を重ねていたゲイのクロードも、パートナーと安定した生活を送っているようだ。セバスチャンは大学の学生を買収して、病院に来させ、如何にレミが優れた教師であったかという芝居をさせてレミを喜ばせる。
 レミの癌はもう末期まで進行しており、手の下しようがなく、レミも痛みに苦しんでいた。セバスチャンはヘロインにより痛みの緩和を図ろうとして、ダイアンを通じてヘロインを使用している彼女の娘のナタリーと知り合う。セバスチャンはナタリーを雇って、ヘロインの投与を含めて父の看護を依頼する。その過程でセバスチャンとナタリーははお互いに心を引かれるようになり、ナタリーはヘロインの使用をやめようと決意して、それを実行する。
レミの癌はもう末期まで進行しており、手の下しようがなく、レミも痛みに苦しんでいた。セバスチャンはヘロインにより痛みの緩和を図ろうとして、ダイアンを通じてヘロインを使用している彼女の娘のナタリーと知り合う。セバスチャンはナタリーを雇って、ヘロインの投与を含めて父の看護を依頼する。その過程でセバスチャンとナタリーははお互いに心を引かれるようになり、ナタリーはヘロインの使用をやめようと決意して、それを実行する。
レミはケベック州の社会主義化に賛成し、病院の労働組合も支持していたので、自分の選択の結果としてお粗末な医療を受けることに対しても文句を言わないと心に決めていたが、その自分に最後の安静を与えてくれたのは、自分が否定していた資本主義社会の中で成功していた息子だった。死を目前にして、あれこれ頑張り遊びまわった割りには自分は何も成し遂げなかったと寂しい反省もするが、意外にも自分の一番の功績は、自分がそれまで功績だとも思っていなかったわが子だということがわかり、安らかに息を引き取るのだった。
ケベック州はカナダの中でも特異な位置を占めている。ここは歴史的には17世紀頃からフランス人の入植がなされた地域であるが、18世紀の七年戦争で英軍に占領された。1776年に英国から独立した米国は、ケベック州の反英の気持ちを知っていたのでアメリカ合衆国に参加するように誘ったが、ケベックは深慮の上、カナダに残ることに決めた。しかし、カナダ独立後ケベック州の反カナダ連邦主義は続き、フランス語をケベック州の唯一の公用語として、今でもケベック住人の半数弱はカナダからの独立を主張している。
1960年代からケベック州では『静かな革命』といわれる流血によらない穏やかな社会主義化が進み、民族主義と社会民主主義(左翼)を柱として、反カトリック、社会主義的医療保険制、スト権を認める強力な労働基準法などが設立された。カナダは英連邦の模範児で、医療や労働条件に関してはヨーロッパに似た穏やかな社会主義を取っているが、ケベックはさらにもう一歩過激なのである。
ドゥニ・アルカン監督は1941年生まれだから、ケベックの静かな革命の影響をもろにうけている。『アメリカ帝国の滅亡』と『みなさん、さようなら』の登場人物もだいたいドゥニ・アルカン監督と同世代かちょっと若いくらい、1986年に40歳前後という設定であろう。彼らは1980年代にはカトリックも資本主義も衰え、頼みのマルクス主義もだめで一体何が人生のドクトリンになるのかと思っていたが、案外資本主義は健在だったんだな、見落としがちだけど、やはり家族が生きていく上での核になるのだなというのが、この映画のオチであろう。それにしても、主演の6人の俳優が二作とも仲良く出演しているのには驚く。17年もあれば、死んでいる人間もいるかもしれないし、俳優を辞めているかもしれないし、俳優としての格の上がり下がりで出演料の交渉も大変だろうが、皆楽しく元気そうに好演している。俳優としてこの作品の価値を認めているのだろうし、なによりもドゥニ・アルカン監督が俳優を惹きつける力があるのだろう。
[映画] グッバイ、レーニン! Good Bye, Lenin!(2003年)
 東ドイツの首都東ベルリンに暮らす主人公のアレックスとその家族。母のクリスティアーネは夫のローベルトが西ドイツへ単独亡命して以来、その反動から熱烈に社会主義に傾倒してしまったという設定。1989年10月七日、東ドイツ建国40周年記念日にクリスティアーネは心臓発作を起こして倒れ、昏睡状態に陥る。彼女は二度と目覚めないと思われたが、8ヶ月後に病院で奇跡的に目を覚ます。しかし、その時にはすでにベルリンの壁は崩壊、東ドイツから社会主義体制は消え去り、東西統一も時間の問題となっていた。アレックスは、母を自宅に引き取ったが、「もう一度大きなショックを受ければ命の保障は無い」と医師から宣告されたため、周囲を巻き込んで、東ドイツの社会主義体制が何一つ変わっていないかのように必死の細工と演技を続ける。しかし、母の告白により、実の父は母を捨てて亡命したのではなく、クリスティアーネはローベルトが西側に逃げた後を追いかけるという約束を破って東ベルリンに留まり、父から来た手紙すらアレックスと姉には見せず隠していたことを知る。クリスティアーネはベルリンの壁の崩壊後3年行き続け、アレックスは自分がうまく現実を母から隠しおおせたと思っているが、実際はどうだったんでしょうね、という感じで幕が閉じる。
東ドイツの首都東ベルリンに暮らす主人公のアレックスとその家族。母のクリスティアーネは夫のローベルトが西ドイツへ単独亡命して以来、その反動から熱烈に社会主義に傾倒してしまったという設定。1989年10月七日、東ドイツ建国40周年記念日にクリスティアーネは心臓発作を起こして倒れ、昏睡状態に陥る。彼女は二度と目覚めないと思われたが、8ヶ月後に病院で奇跡的に目を覚ます。しかし、その時にはすでにベルリンの壁は崩壊、東ドイツから社会主義体制は消え去り、東西統一も時間の問題となっていた。アレックスは、母を自宅に引き取ったが、「もう一度大きなショックを受ければ命の保障は無い」と医師から宣告されたため、周囲を巻き込んで、東ドイツの社会主義体制が何一つ変わっていないかのように必死の細工と演技を続ける。しかし、母の告白により、実の父は母を捨てて亡命したのではなく、クリスティアーネはローベルトが西側に逃げた後を追いかけるという約束を破って東ベルリンに留まり、父から来た手紙すらアレックスと姉には見せず隠していたことを知る。クリスティアーネはベルリンの壁の崩壊後3年行き続け、アレックスは自分がうまく現実を母から隠しおおせたと思っているが、実際はどうだったんでしょうね、という感じで幕が閉じる。
『グッバイ、レーニン! 』はコメディーであり、その底には風刺と機知がある。東ベルリンに住んでいる人間がベルリンの壁の崩壊の前は「それを得られるなら命を捨ててもいい」と思ったほど渇望していた自由も、壁の崩壊の崩壊後の経済混乱、失業、社会混乱、今まで誇りに思っていたものの喪失などを目の当りにすると、自由社会というのは思ったようなバラ色のものではなかったという苦い現実を感じてしまう。しかしそれよりもこの映画に深く流れているのは、自分が信じていたもの、信じさせられていたものは嘘だったいうことへの自覚である。それを悔やんだり、誰かを責めているというのではない。普通の市民は社会主義体制の中では与えられたプロパガンダを信じて生きていくだろうし、社会が急激に変わったら変わったなりに、一生懸命適応していくものだ。映画では、アレックスとその周囲の人々はの転換期をさらっとしたユーモアで描くのだが、母親にはやはり古い価値を信じたまま安らかに死んでほしいという思いもある。この映画がドイツで大ヒットをしたのも、価値観の急激な変化やそれに伴う混乱こそあれ、順調に民族統一を成し遂げたドイツ社会の安定というものが背後にあるのだろう。その時は苦しかったが、ドイツ人には、20年後の今、ユーモアで過去の混乱を振り返る余裕があるのだ。
 急激な体制の変化を風刺と笑いで描こうと意図は価値のあるアプローチだと認めるとしても、残念なことに、この映画が素直に面白いのは前半だけで、長い映画の後半に入ると、同じ試みの繰り返しで話はだらだらと退屈になってくる。アレックスの善意の努力も見当はずれになり、「いつまでだまし続けるのか?正直に母に現実を告げなさい。」という恋人の批判も、「だまし続ける生活はストレスだらけだ」という姉の怒りもお構いなく、一日中偽造に奮闘するアレックスを見ていると、だんだん笑えなくなってくる。おまけに風刺の対称は何なのかがわからなくなってさえくる。「冷戦の終了は甘いものばかりではなかった」というセンチメントを表現したいのか、或いはへたをすればそれは「なんだ、社会主義の方がましだったじゃないか。東ドイツは米ソに次いで多くの金メダルをオリンピックで獲得していた偉大な国だったんだ。」というメッセージを受け取ってしまう人もいるかもしれない。
急激な体制の変化を風刺と笑いで描こうと意図は価値のあるアプローチだと認めるとしても、残念なことに、この映画が素直に面白いのは前半だけで、長い映画の後半に入ると、同じ試みの繰り返しで話はだらだらと退屈になってくる。アレックスの善意の努力も見当はずれになり、「いつまでだまし続けるのか?正直に母に現実を告げなさい。」という恋人の批判も、「だまし続ける生活はストレスだらけだ」という姉の怒りもお構いなく、一日中偽造に奮闘するアレックスを見ていると、だんだん笑えなくなってくる。おまけに風刺の対称は何なのかがわからなくなってさえくる。「冷戦の終了は甘いものばかりではなかった」というセンチメントを表現したいのか、或いはへたをすればそれは「なんだ、社会主義の方がましだったじゃないか。東ドイツは米ソに次いで多くの金メダルをオリンピックで獲得していた偉大な国だったんだ。」というメッセージを受け取ってしまう人もいるかもしれない。
しかし、私たちは東ドイツのオリンピックの栄光の陰には、国家をあげての薬物の使用という事実があったことを忘れてはいけないだろう。それも、薬物はアスリートの同意なしに与えられていたのである。その一人として東ドイツの砲丸投げの一人者ハイジ・クレーガーがいる。彼女は自分がそうと知らないうちに継続して与えられたステロイドホルモンのために体を壊し競技生活を引退したが、今は性転換手術の後男性としてアンドレア・クレーガーという名前で生きている。彼は2004年のニューヨークタイムズのインタビューで「男性として暮らせる今の生活には満足しているが、自分の同意なく政府機関から薬物を与えられてこの状況に至ったというその過程には非常に怒りを感じる。」と述べている。
風刺の意図をどれだけ明確にするかというのは、コメディーを作る場合、高い技術を要求されると思うが、やはりもう少し姉や恋人のまっとうな意見に影響されるアレックスを見たかった。聴衆の中には、最後にはアレックスの行動に辟易する人が結構いるような気がする。その辟易とした時点で笑いも止まってしまうのだ。