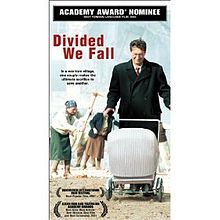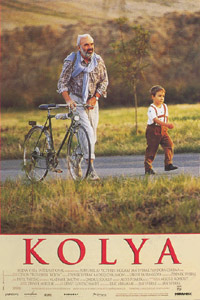この映画は、ルーマニアの首都ブカレストに住む17歳のエバの1989年の人生のスケッチである。1989年はルーマニアでは共産党書記長のニコラエ・チャウシェスクが処刑され、共産主義独裁政権が倒された年であるが、この映画は、反抗的で無表情で無愛想で、なげやりでいい加減にみえる(しかし外見は可愛らしくて、ボーイフレンドと話す時だけはちょっと笑顔をみせる)エバが、社会主義政権の有力者の息子アレクサンドラと付き合いつつも、ニコラエ・チャウシェスク暗殺未遂の容疑で両親が行方不明になっているアンドレーにも興味を示し、二人でドナウ川を渡ってユーゴスラビアへの亡命を企む。結局エバは「や~めた」と言って川を横断するのを中断し、一人でブカレストに帰って来て、怒った両親から、一家の立場を安全にするためにアレクサンドラともっと仲良くしてほしいと頼まれる。エバはアレクサンドラが最近購入したぼろアパート(しかしルーマニアの水準では高級アポートかもしれない)に目を奪われる。結局二人は何となく男と女の関係になってしまい、帰宅したエバは得意満面で「私たち婚約したわ!!」と宣言するのだが、その直後に流血革命が起こり、それまで鬱屈として体制の言いなりになっていたかに見える大人たちが、突然嬉々として破壊活動を始める。この映画は流血革命のあと上流階級から滑り落ちたアレクサンドラの一家、無事ユーゴスラビア経由でイタリアに辿りついたアンドレー、得意満面に国際路線の客船搭乗員としてキャリアを追求するエバを短く描いて終わる。
この映画は、ルーマニアの首都ブカレストに住む17歳のエバの1989年の人生のスケッチである。1989年はルーマニアでは共産党書記長のニコラエ・チャウシェスクが処刑され、共産主義独裁政権が倒された年であるが、この映画は、反抗的で無表情で無愛想で、なげやりでいい加減にみえる(しかし外見は可愛らしくて、ボーイフレンドと話す時だけはちょっと笑顔をみせる)エバが、社会主義政権の有力者の息子アレクサンドラと付き合いつつも、ニコラエ・チャウシェスク暗殺未遂の容疑で両親が行方不明になっているアンドレーにも興味を示し、二人でドナウ川を渡ってユーゴスラビアへの亡命を企む。結局エバは「や~めた」と言って川を横断するのを中断し、一人でブカレストに帰って来て、怒った両親から、一家の立場を安全にするためにアレクサンドラともっと仲良くしてほしいと頼まれる。エバはアレクサンドラが最近購入したぼろアパート(しかしルーマニアの水準では高級アポートかもしれない)に目を奪われる。結局二人は何となく男と女の関係になってしまい、帰宅したエバは得意満面で「私たち婚約したわ!!」と宣言するのだが、その直後に流血革命が起こり、それまで鬱屈として体制の言いなりになっていたかに見える大人たちが、突然嬉々として破壊活動を始める。この映画は流血革命のあと上流階級から滑り落ちたアレクサンドラの一家、無事ユーゴスラビア経由でイタリアに辿りついたアンドレー、得意満面に国際路線の客船搭乗員としてキャリアを追求するエバを短く描いて終わる。
エバは最初から最後まで無表情で傲慢で、彼女の内面は全く描かれていない。政権の中枢を象徴するアレクサンドラと反体制の象徴のアレックスを行き来し、双方のハンサムな若者をそれなりに好きなのだから、ティーンネージャーの愛とはこういうものだろうと思わせる。ソ連の衛星国の中でも後進国のルーマニアの荒涼とした様子、首都ブカレストでさえ荒れ果てており、両親が何をしているのかわからないが、いつも暗鬱な顔をして疲れていて、子供に対する関心もない。暮らし向きは悪くないはずだが、家の中も荒れ果てている感じだし、食事もスープとパンだけという粗末さだ。政治議論は全くなく、政治に係わることも恐れている大人たちだが、その荒廃した日常生活の描写が、行き着く所まで行き着いたルーマニアの独裁社会主義政権の停滞の実態を表し、説明の言葉も必要ない。
 ルーマニアの映画界は1980年後半から新しい活動の兆しをみせ、2000年代にはカンヌ映画祭を中心に注目を浴びるようになった。そのテーマは社会主義国から自由経済国家体制への移行や、チャウシェスク体制の批判が中心であるが、編集未完成のようなドキュメンタリー風のミニマリストの作品が多いようだ。これを「新鮮」というか、「アマチュアリズム」というかは議論の分かれるところであるが、洗練された映画技巧を誇るポーランドやチェコやハンガリーの映画を観たあとでは、ルーマニアの映画はまだこれからだという感じがする。カンヌでルーマニア映画が一時もてはやされ、この映画でエバを演じたドロティア・パトレは主演女優賞までもらっているが、これはルーマニアに対する応援という西欧諸国の気持ちもあるのだろう。この映画もストーリが唐突であり、冬と夏が何回も繰り返されるので何年かにわたってのお話だと思っていたら、たった一年である。そのへんの正確さに期すという態度はない。またエバを演じるドロティア・パトレが老け顔で30歳くらいに見え、母親を演じる若作りの女優と全く似ていないし、二人は姉妹か友達という感じに見える。確かに両女優とも結構美人なのだが、これでいいのだろうかと思ってしまう。何となく気分のままに、細かいことに拘らず作った映画という感じで、世界には凝りに凝って作る監督が多い中で、さてルーマニアの映画はこれからどういう方向に行くのだろうかと思わされる。
ルーマニアの映画界は1980年後半から新しい活動の兆しをみせ、2000年代にはカンヌ映画祭を中心に注目を浴びるようになった。そのテーマは社会主義国から自由経済国家体制への移行や、チャウシェスク体制の批判が中心であるが、編集未完成のようなドキュメンタリー風のミニマリストの作品が多いようだ。これを「新鮮」というか、「アマチュアリズム」というかは議論の分かれるところであるが、洗練された映画技巧を誇るポーランドやチェコやハンガリーの映画を観たあとでは、ルーマニアの映画はまだこれからだという感じがする。カンヌでルーマニア映画が一時もてはやされ、この映画でエバを演じたドロティア・パトレは主演女優賞までもらっているが、これはルーマニアに対する応援という西欧諸国の気持ちもあるのだろう。この映画もストーリが唐突であり、冬と夏が何回も繰り返されるので何年かにわたってのお話だと思っていたら、たった一年である。そのへんの正確さに期すという態度はない。またエバを演じるドロティア・パトレが老け顔で30歳くらいに見え、母親を演じる若作りの女優と全く似ていないし、二人は姉妹か友達という感じに見える。確かに両女優とも結構美人なのだが、これでいいのだろうかと思ってしまう。何となく気分のままに、細かいことに拘らず作った映画という感じで、世界には凝りに凝って作る監督が多い中で、さてルーマニアの映画はこれからどういう方向に行くのだろうかと思わされる。
1989年というのは、中国で天安門事件が起こり共産主義の徹底が強化された年であるが、東欧では比較的平和的に共産主義独裁国家が倒された年でもある。1978年にポーランド出身のヨハネ・パウロ2世がローマ教皇に就任した時は、誰もこれが冷戦の終結に繋がる一歩だとは思わなかっただろうが、実際にヨハネ・パウロ2世が冷戦の終結になした貢献は偉大なものなのではないか。ポーランド人は何か心の中で信じるもの、精神的な希望を感じたのである。同時に現実的でカリスマのある労働運動の指導者レフ・ヴァウェンサ(日本ではワレサと呼ばれた)議長の登場である。彼が『連帯』という言葉で風向きを変えようとした時、東欧を見つめる世界の大半の人間は「ああ、またハンガリー動乱やプラハの春が今度はポーランドで繰り返されるのか」と思っただろう。しかし、ヴァウェンサの態度は異なっていた。彼は非常に二枚腰で柔軟であり、モスクワの反応を用心深く確認しながら一進一退で、非暴力を主張し穏健に辛抱強くポーランドの民主化を進めて行ったのだ。
ハンガリーも同じ「大人の国」であった。もとから、ハンガリーは自国はオーストリアのような精神の先進国であるという自負があった。1985年年にソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ政権が始めた「ペレストロイカ」でソビエト連邦が持っていた東側諸国の共産党国家に対する統制、いわゆる「ブレジネフ・ドクトリン」が撤廃されると、ハンガリーは巧みにこの動きを利用して、1989年5月にハンガリーとオーストリア間の国境を開放した。6月にはポーランドで選挙によって非共産党政権が、そして10月にはハンガリーでも非共産党政権が樹立された。
ハンガリー・オーストリア国境を東ドイツ市民が大挙して集団越境し、オーストリア経由で西ドイツに亡命することが可能になった今、ベルリンの壁の存在意義は喪失した。11月10日にベルリンの壁は破壊されたのである。それはチェコスロバキアやルーマニアにおいて、民主化を要求する市民たちを大いに励ました。チェコスロバキアでは11月17日にビロード革命と呼ばれる無血革命が起こった。しかしルーマニアでは独裁者ニコラエ・チャウシェスクの処刑という血生臭い結果となった。
ニコラエ・チャウシェスクは1967年から1989年までの22年間ルーマニアの独裁者であった。最初はプラハの春の鎮圧に反対してソ連支援の軍隊を出すことを拒絶したり、 ユーゴスラビアと共に親西側の態度を表明し、IMF やGATTに加入し西側経済にも同調し、イスラエルをソ連衛星国の中で唯一承認して外交関係を立ち上げ、東側諸国が軒並みボイコットした1984年のロサンゼルスオリンピックにおいても、ルーマニアは唯一ボイコットをせず参加した。ニコラエ・チャウシェスクは西側諸国では非常な好印象を持たれていたし、国民の支持も高かったのである。しかし残念ながら、権力の座に長くいすぎたようである。彼は次第にルーマニアの国家体制を北朝鮮の朝鮮労働党や中国共産党の方向に向けようとし始めた。
ニコラエ・チャウシェスクの不人気を決定的にしたのは、彼の経済政策の失敗である。西側諸国から人気のあったルーマニアであるから、西側からの資金援助を得ることは容易であったが、これは両刃の刃であった。ルーマニアはその多額の融資の返還に苦しみ、国内経済を犠牲にしルーマニア人の生活が大変貧窮したのである。国内では食糧の配給制が実施され、無理な輸出が優先されたのでルーマニア国民は日々の食糧や冬の暖房用の燃料にも事欠くようになり、停電が頻繁になった。この辺はこの映画でも描かれている。
2012年の「中東の春」ではTwitterによる交信がリアル・タイムで機能し、革命を推進したが、1989年の「東欧革命」ではテレビが大きな役割をしめている。ルーマニアの国民はテレビを通じてハンガリーで、ポーランドで、チェコスロバキアで、東ドイツで何が起こっているかを知ることができた。この様子もこの映画で詳しくうかがうことができる。