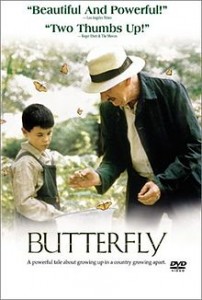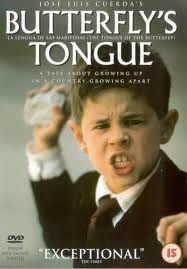スペインのバルセロナ、移民たちが暮らす貧しい地域に住むウスバルは、非合法移民に仕事を与え仲介料を受けるという中で、非常に貧しい生活を送っていた。また彼は死者の魂と語ることができるという能力を持っていたので、霊媒師としてお葬式で死者との会話を親族に頼まれることもあった。妻は病的な躁鬱症で子供を育てることが出来ず、ウスバルは妻と別居して2人の幼い子供たちと暮らしていた。そんな中、彼は末期ガンであり、もう余命が幾ばくもないと宣告される。ウスバルは、セネガルからの非合法移民で夫は強制送還され、乳飲み子と暮らしているイゲーとひょんなことから共同生活を始めることになる。心優しく子供の面倒をみて自分の看病もしてくれるイゲーに心を許したウスバルは、全財産をイゲーに与え、自分の死後子供の面倒を見てくれと頼む。この映画はイゲーがそのお金を手にセネガルに帰国しようとこっそりアパートを出た日にウスバルが死ぬというところで終わっている。
スペインのバルセロナ、移民たちが暮らす貧しい地域に住むウスバルは、非合法移民に仕事を与え仲介料を受けるという中で、非常に貧しい生活を送っていた。また彼は死者の魂と語ることができるという能力を持っていたので、霊媒師としてお葬式で死者との会話を親族に頼まれることもあった。妻は病的な躁鬱症で子供を育てることが出来ず、ウスバルは妻と別居して2人の幼い子供たちと暮らしていた。そんな中、彼は末期ガンであり、もう余命が幾ばくもないと宣告される。ウスバルは、セネガルからの非合法移民で夫は強制送還され、乳飲み子と暮らしているイゲーとひょんなことから共同生活を始めることになる。心優しく子供の面倒をみて自分の看病もしてくれるイゲーに心を許したウスバルは、全財産をイゲーに与え、自分の死後子供の面倒を見てくれと頼む。この映画はイゲーがそのお金を手にセネガルに帰国しようとこっそりアパートを出た日にウスバルが死ぬというところで終わっている。
映画の最後は非常に曖昧である。イゲーは結局帰って来たともとれるし、イゲーは帰ってこず「私、今帰って来たわ」という彼女の声はウスバルの幻想とも取れるし、娘がイゲーに代わって返事をしているようにも見える。穿った解釈をすれば、大金を持ったイゲーは強盗に殺されて亡霊だけが帰って来たようにも取れる。この映画を議論しているディスカッションサイトを覗いてみると、人々は次のように論議している。「結局イゲーは帰って来たの?」「あの人いい人だったから、金を持ち逃げしたなんて悲しいな」「イゲーの声はウスバルの幻想だよ」「いや、監督のインタビューでは彼女は帰ってきたと言っている」「え、そう?それならうれしいな」「いや~、あれで全財産を持ち逃げされたら救いが無いからな~」
何と優しい会話であろうか。監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥもきっとたくさんの瞳が潤んだファンから同じことを何回も聞かれたのだろう。監督として、これだけ聴衆の心を取り込んだ映画を作れたということは何と監督冥利に尽きることだろう。私もイゲーは結局ウスバルのところに帰ってきたと思う。
 バルセロナは今ロンドンに次いで世界で(パリやニューヨークを押さえて!!)2番目にファッショナブルな街だと言われているそうだ。ウディ・アレンの「それでも恋するバルセロナ」は観光客から見る美しい表の顔を描いているが、この映画はその裏の顔を描いている。バルセロナは古来カタルーニャ人の住む地域であり、マドリッドを中心とするスペイン人とは対立関係にあった。フランコはカタルーニャ文化を崩壊させるため、スペイン人のカタルーニャ地方への移住を推奨し、そこではカタルーニャ語を話すことを禁じたという。カタルーニャ人の中でも更に底辺の人間はバルセロナの場末に押し込められ、その人々は「チャルネゴ」と呼ばれるようになった。ウスバルは「チャルネゴ」であり、彼の父はフランコの政策に反対して命が危なくなり、国外逃亡し、若くしてメキシコで死んだという設定である。
バルセロナは今ロンドンに次いで世界で(パリやニューヨークを押さえて!!)2番目にファッショナブルな街だと言われているそうだ。ウディ・アレンの「それでも恋するバルセロナ」は観光客から見る美しい表の顔を描いているが、この映画はその裏の顔を描いている。バルセロナは古来カタルーニャ人の住む地域であり、マドリッドを中心とするスペイン人とは対立関係にあった。フランコはカタルーニャ文化を崩壊させるため、スペイン人のカタルーニャ地方への移住を推奨し、そこではカタルーニャ語を話すことを禁じたという。カタルーニャ人の中でも更に底辺の人間はバルセロナの場末に押し込められ、その人々は「チャルネゴ」と呼ばれるようになった。ウスバルは「チャルネゴ」であり、彼の父はフランコの政策に反対して命が危なくなり、国外逃亡し、若くしてメキシコで死んだという設定である。
この映画は、ガンという病気と、最底辺の生活という暗いテーマを描くのだが、その暗さに拘わらず共感できることがたくさんあり、見終わったあとも何か一筋の希望がある。というのも、ウスバルが非常に心の美しい愛情深い人間に描かれているからだ。しかし、彼は完璧な人間ではない。題名がBeautiful ではなく Biutiful になっているのは、彼が完璧に美しい人間になるには何かが欠けているからである。何が欠けているかというと、「賢さ」である。彼は最悪の環境で生きている中国人の移民に同情してストーブを買ってあげるが、安物のストーブから出るガスで、結局その大部屋に住んでいる中国人の移民は皆死んでしまう。裏社会で金を稼いでいるので、銀行に預金するでもなく、ガンになっても保険はないし、貧しい子供の死後をどうするかという決断もできず、安心して死ぬこともできない。頼れる人は他人のイゲーしかおらず、彼女には全財産を与えてしまう。しかし、この「賢さ」とか「処世術」とかは親から、社会から学ぶものである。ウスバルにこういった叡智を授けてくれる両親がいないのは、フランコの抑圧の結果だとも言えるし、「チャルネゴ」として差別されている限りは教育も満足に受けられないだろうし、まともな職にもつくことができないだろう。悪いシステムの中での悪循環である。この映画は愚かでも美しい心のウスバルを描くことで間接的に社会のシステムを批判しているかのようだ。ウスバルが死人と交流できるというのも、彼が純粋だが教育がないということの極端な結果かもしれない。
スサンネ・ビア監督の『アフター・ウェディング』を観た時は、監督はガンを物語りの狂言回しの知的道具として使っているという印象を受けて、その映画は好きになれなかった。しかし、この『BIUTIFUL』の中でのガンの扱い方には納得が行った。監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥは死というものを心で感じて理解している人なのだと思った。ウスバルの霊媒師仲間の女性がウスバルに「あなたは死んでいく。身の回りの整頓をしなさい」と静かに語るシーンが印象的である。人は皆自分が死ぬとは思っていないが、たいていの場合は死は突然にやって来る。しかしガンでの死は静かに時間をかけてやって来る。死の準備が出来、自分の人生を振り返る時間が与えられるのである。そして現在ではガンはもはや『死に至る病』ではない。ガンからの生還は可能なのである。私は、アメリカで暮らしているが、ガンから生還した人に何人も出会ったが、多くの人が「ガンを患ったことは、一番幸運なことだった」と言う。私はその気持ちが100%理解できる。
イニャリトゥ監督の映画は全作観ているが、彼の心の根底にあるセンチメントは日本人にも分かり合える『一期一会』とか『輪廻』である。人々はこの世では意外な所で無限に繋がっており、その出会いから人生が展開していくというのが彼の思いであろう。だから、人間の繋がりは国境を越えて拡がって行くものである。その現世での精神の交流が死後にはどうなるかということは、彼は語っていない。しかし、彼は、心というものは、自分が死んだ後でも、子供や新世代の人間に受け継がれていくと信じているのではないか。だから、次の世代のために生きることは、自分のために生きることでもある。
イニャリトゥ監督はメキシコ出身だが、現在は家族と共にロサンゼルスに住んでいる。別にそれは祖国メキシコに対する裏切りでも何でもなく、仕事の関係、そして最近特に治安が悪くなっているメキシコで子供を育てることへの不安、或いは二カ国に住むことによって自分が複数の眼を持てるという環境が好きなのかもしれない。私がイゲーが結局戻ってきたと思うのも同じ理由からである。彼女は夫が強制送還された時に、夫から、お前は絶対にセネガルに帰ってくるな、ここで子供と頑張れと言われている。子供はスペイン生まれなので、スペイン人だし、子供の母親として彼女もスペインに滞在できる。セネガルに帰っても貧困生活が待っているだけで、最下層としてのバルセロナの生活は、それに比べたら楽なものであるし、子供の将来の希望もある。親としての決心なのである。
この映画は2010年のアカデミー最優秀外国語賞をスサンネ・ビア監督の『未来を生きる君たちへ』と競って負けた。スサンネ・ビア監督は「人間ってちょっとした小さいことで、復讐心を抱いちゃうでしょ。それが面白いな~と思ってこの映画を作りました」と言っている。アカデミー賞を取れなかったから、この映画が『未来を生きる君たちへ』より劣っているなんていうことは全くない。少なくとも、イニャリトゥ監督は「面白いな~と思ってこの映画を作りました」とは言わないだろう。