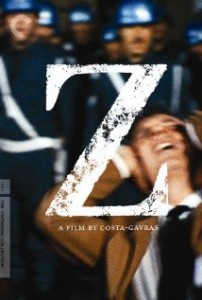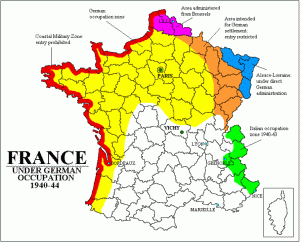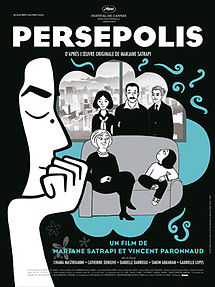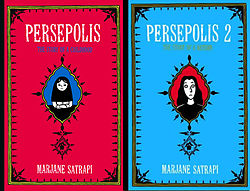この映画はどこか『屋根裏部屋のマリアたち』に似ているが、別に美男美女が出てくわけでもないし、もっと地味で見過ごされてしまう話である。『屋根裏部屋のマリアたち』での恋の障壁は、わかり易い『人種』とか『社会階層』の差であるが、ここでは恋の障壁は、安定した中産階級の中での個人の教養の差というか、人生の楽しみ方や嗜好の差である。しかし、人生を静かに深く楽しむ『大人の人間』にはこの映画を心から推薦したくなる、そんな映画なのである。
この映画はどこか『屋根裏部屋のマリアたち』に似ているが、別に美男美女が出てくわけでもないし、もっと地味で見過ごされてしまう話である。『屋根裏部屋のマリアたち』での恋の障壁は、わかり易い『人種』とか『社会階層』の差であるが、ここでは恋の障壁は、安定した中産階級の中での個人の教養の差というか、人生の楽しみ方や嗜好の差である。しかし、人生を静かに深く楽しむ『大人の人間』にはこの映画を心から推薦したくなる、そんな映画なのである。
またハリウッド映画の大げさな表現、たとえば腹が立てば殴る、悔しければ物を投げつけるというテクニックに飽き飽きしている人に是非観てもらいたな、と思う。この映画に出てくる人物は皆それぞれの意味で善男善女であるが、それでも本当に自分が幸福にしてあげれて、幸福にしてもらえる人を捜すためには、性格の良さを超えた、人間の嗜好というものが致命的な役割を持つという当たり前のことをユーモアと仄かな哀歓で描いている。そしてその恋愛観といいユーモアの感覚といい全くフランス的なのである。フランス映画が好きな人には全く説明が不要であろう。
カステラは中堅企業の社長。金はあるが、若い子からはチビ、デブ、ハゲとからかわれかねない風采で、自分の事業を運営すること以外何の教養も趣味もない。イランの会社とビジネスをすることになり、その業務契約の中に彼の身辺を守るためボディーガードをつけるという項目がついたので、元警察官のフランクが雇われる。イラン人と会話をするために英語が必要となり、契約はカステラが英語の個人授業をつけることも要求するが、彼は英語の授業に興味もなく、英語教師のクララもすげなく追い返してしまう。
自分の姪が女優の卵なので、彼女が出ている舞台を妻とお義理で見に行ったが、演劇に興味も持たなかったカステラは思いもかけず、その劇に感動してしまい、自分を感動させた女優が自分の英語教師だと気がつく。そう、彼は恋に落ちたのだ。それから彼の彼女への熱烈(と本人は思っているのだが、傍から見れば滑稽)なアタックが始まる。この映画はそのカステラとクララを含む人物群像の、異性への(そして人生への)心の惹かれ方を描く。
カステラの妻はインテリア・デコレーターで、自宅を少女趣味でゴタゴタ飾り、カステラも自分は美的センスがないのでそれでいいと思っていた。しかしカステラはクララと彼女の取り巻きの芸術家と付き合っていくことにより、自分にも好みがあったということに気づく。その過程で彼は、妻は自分の気持ちを無視し、彼女の考えや好みだけが正しいと思い、自分より動物のことだけを気にかけ、表面的なことにしか興味がない人間に感じ始め、妻への心が離れていく。自分の好みに目覚めたカステラは花模様だらけの家に暮らすことがだんだん息苦しくなってくる。
カステラは自分と働く一流大学出身のエリートのビジネス・コンサルタントの高圧的な態度に劣等感を抱き、彼は自分を馬鹿にしていると嫌っていた。しかしそのコンサルタントがカステラと働くことに疲れ辞表を出した時のほっとした人間的な表情を見て、コンサルタントは自分の職務を熱意を持って執行するがために堅い態度を取っていただけだったが、彼は自分の仕事に取って大切な人間だとわかり、カステラは謙虚なな態度で彼が辞意を翻すよう懇願する。
カステラのボディーガードのフランクは一見クールでニヒルな悪っぽい男、カステラの運転手のブルーノは善良すぎるお人よしだが、二人は仕事を通じて仲良くなる。ブルーノはクララたち芸術仲間がたむろするバーにタバコを買いに行き、そこでバーテンダーをしているマニと知り合う。マニは優しい女性で、彼女は最初はブルーノの優しい部分に引かれて付き合うが、ブルーノを通じてフランクに会った瞬間、フランクの中にある虚無的で暗い部分と自分の中にある暗さが稲妻のように閃きあい一瞬で恋に落ちる。
フランクは一見虚無的に見えるが、心の中には自分が捨てたと思った正義感が残っていた。彼はマニが麻薬の売買で生計を立てているのを止めようとするが、マニはそれが気にいらない。そしてある日、自分の元同僚が、法律に隠れて悪事を働いていた大物を遂に逮捕することに成功したというニュースを目にする。フランクとその同僚はその大物を追っていたが、その大物は常に逃げるのに成功していた。フランクはそんな現実に嫌気がさして警官を辞めたが、同僚は決して捜査を諦めなかった。その事実はフランクに自分とマニとの関係を再考するきっかけとなった。
クララは最初は自分に付き纏う教養のないカステラの存在を迷惑に思っていた。しかし同時に自分の芸術仲間がカステラの教養の無さを軽蔑しているのに、彼の金を目当てにパトロンになってもらい、金を貰っているのに彼を馬鹿にするのをやめないという状況がいやになってきた。クララは次第に、カステラにも彼なりの鑑賞眼があり、その目で自分を女優として、人間として、そして女性として評価してくれているのに気がつき、彼に心を開いていく。
ブルーノはお人よし過ぎるということで恋人にもマニにも振られてしまう。自分の好きなフルートを吹くために街の素人オーケストラに入るが、そこで彼と波長の会いそうな優しそうな女の子に憧れの目で見られるというところでこの映画は終わる。とても前向きな気持ちを与えてくれる終わり方である。
要するにこの映画は何かに惹かれてしまうその過程のミステリーを描いている。その感情はある日突然稲妻のようにやって来るかもしれないし、思いもよらないところからじっくりとやって来るかもしれない。自分の中にはいろいろな人格や価値観が混ざっているが、人間は結局その中で自分の本当に大切な嗜好や価値観に基づいて異性や人生の機会を選んでいくという当たり前のことを、素敵な感覚で表現している映画である。