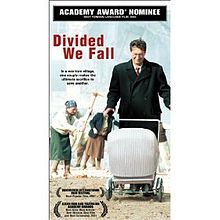この映画の最初の2時間ほどは、ソ連の田舎にある芸術村で夏を過ごす家庭の団欒を描くことに終始し、まるでチェーホフの世界を眺めているようである。そうするうちに、一家の父親はロシア革命の伝説的な赤軍英雄のコトフ大佐であり、その若い妻はどうも元貴族の家系であり、彼女の一族がそこに召使と一緒に住んでいることから、この芸術村は妻の一家の別荘であったらしいと推測がつく。大佐は妻との間に ナージャという可愛らしい娘がいる。突然ディミトリという若くてハンサムな貴族風の芸術家が訪ねて来て、妻の家族に大歓迎される。そうこうしているうちに、ディミトリも元貴族で妻の嘗ての恋人であるということが知らされ、大佐以外は皆フランス語で楽しげに会話を始め、フランス語を知らない大佐はちょっと仲間はずれになる。これは恋の三角関係なのかと思っているうちに最後の20分で、ディミトリは実は秘密警察の一員であり、スターリンの命令でコトフ大佐を逮捕に来たという裏の背景がわかってくる。元貴族だから白軍派のはずなのに、ディミトリはなぜ赤軍の英雄のコトフ大佐を逮捕する権限を持っているのか、と観ている者は煙につつまれるはずだ。
この映画の最初の2時間ほどは、ソ連の田舎にある芸術村で夏を過ごす家庭の団欒を描くことに終始し、まるでチェーホフの世界を眺めているようである。そうするうちに、一家の父親はロシア革命の伝説的な赤軍英雄のコトフ大佐であり、その若い妻はどうも元貴族の家系であり、彼女の一族がそこに召使と一緒に住んでいることから、この芸術村は妻の一家の別荘であったらしいと推測がつく。大佐は妻との間に ナージャという可愛らしい娘がいる。突然ディミトリという若くてハンサムな貴族風の芸術家が訪ねて来て、妻の家族に大歓迎される。そうこうしているうちに、ディミトリも元貴族で妻の嘗ての恋人であるということが知らされ、大佐以外は皆フランス語で楽しげに会話を始め、フランス語を知らない大佐はちょっと仲間はずれになる。これは恋の三角関係なのかと思っているうちに最後の20分で、ディミトリは実は秘密警察の一員であり、スターリンの命令でコトフ大佐を逮捕に来たという裏の背景がわかってくる。元貴族だから白軍派のはずなのに、ディミトリはなぜ赤軍の英雄のコトフ大佐を逮捕する権限を持っているのか、と観ている者は煙につつまれるはずだ。
ニキータ・ミハルコフがこの映画の監督、脚本、主演を勤めており、大佐の娘ナージャを演じた少女は彼の実の娘である。ニキータ・ミハルコフの兄は『僕の村は戦場だった』を監督したアンドレイ・タルコフスキーの親しい友人のアンドレイ・コンチャロフスキーである。ニキータ・ミハルコフの父はソ連国歌の作詞家であるセルゲイ・ミハルコフである。セルゲイ・ミハルコフによるソ連国歌は眩しいまでのスターリン崇拝の歌で、1944年に国歌となったが、セルゲイ・ミハルコフはスターリン批判の影響で1977年にはその歌詞の一部を書き換え、その後2001年には新しいロシアのために完全に歌詞を変更している。
スターリンの大粛清は1930年代に起こっているが、1953年のスターリンの死後、ソ連共産党第一書記ニキータ・フルシチョフにより公式にスターリン批判が始まり、スターリンの個人崇拝は公的に批判された。1964年のフルシチョフの失脚後、レオニード・ブレジネフの政権下では一時改革派の力が衰え、チェコに軍事介入するプラハの春事件を起こしたりというジグザグもあったが、1985年にはミハイル・ゴルバチョフによって再びスターリン批判が再確認され、多くの犠牲者たちの名誉が回復された。この映画は1994年に作られているから、或る程度の言論の自由も保証されているはずだが、この映画の中でのスターリン批判は非常に象徴的である。そのシンボリズムはフランコの弾圧を恐れて、批判の気持ちをシンボリズムに託し、恐ろしいほど美しく妖しい映像をつくったスペインの現代映画に似ている。
この映画も映像の美しさ、シンボリズムの怪しさには恐るべきものがある。映画の中で具体的な粛清の恐ろしさを最小限に押さえ、はかない美を描くことに徹底したのはなぜだろうか。私はニキータ・ミハルコフという人間を知らないので何ともいえないが、私が感じるのは、ニキータ・ミハルコフという人は政治的な人ではないのではないか、ということである。彼にとって美しい心や、何か美しいものが一番大切なのであり、革命という仮面を被った暴力行為や、粛清という名の殺人行為は、それが醜いから、美しくないから、憎いのである。しかし、彼自身は繊細な心で政治というものに引っかかってしまっても、それを器用に扱っていくという資質の人ではないと思う。彼を理解するためには、彼が「親友で、一番大切な心の友」と常に呼んでいた黒澤明のことを考えれば、わかりやすいのではないか。黒澤がスターリンの大粛清を映画化するとしたらどうしたであろうか?私の答えは、「黒澤はそんな映画を作らなかっただろう」ということだ。たとえスターリンの大粛清の真実を知っていたとしてもである。たとえ、たとえだが、もし作ったとしても、非常にシンボリックな映画になったであろう。こう考えるとこの映画の極端なシンボリズムにも納得がいくのではないか。
しかし、ニキータ・ミハルコフという人は正直に自分の気持ちを表現する人である。彼は ボスニア戦争で一方的に犯罪者的な判断を下されて国際的な悪漢にされてしまった感のあるセルビア人を支持し、「民族としての誇りを忘れないでほしい」と述べ、セルビアの対コソヴォ政策も支持している。またウラジーミル・プーチンのリーダーシップにも支持の姿勢を明らかにしている。他の人の思惑はとにかく、自分の感情を正直に認めるタイプの人のように思われる。彼の政治信念を彼の言葉を借りていえば「個人的な考えとして、私は1917年以降のいかなる政府も合法的とは認めていない。なぜなら彼らの権力は暴力と流血とによって得たものだからです。」ということになろうか。だから『太陽に灼かれて』は革命という名の“偽りの太陽”に灼かれた犠牲者たちに捧げられているのであろう。ある日突然、何の前ぶれもなく連行され、家族たちにもその後がどうなったのか知らされなかった人々。大衆の前での偽りの公開裁判で晒し者にされた後で処刑された人々。全く政治に関係ないのに、逮捕されて殺された人々。この映画はそういう人々へのニキータ・ミハルコフとしての鎮魂歌なのであろう。
 大粛清は、当時のソビエト連邦(ソ連)の最高指導者ヨシフ・スターリンが1930年代にソ連邦でおこなった大規模な反対陣営に対する政治弾圧を指す。スターリンに対抗したと看做された者は全て見せしめ裁判でスパイ罪などの自白を強要され死刑の宣告を受けたもので、その対象は幹部政治家のみならず、一般党員や民衆にまで及んだ。その目的はスターリンが自分の政敵を殺すこと、なかなか進まぬ経済の発展への大衆の不満を「裏切り者への憎しみ」に向けてそらすことであった。この粛清はついには革命を成功させた赤軍の英雄や、尊敬されている芸術家、そして海外からソ連に安全を求めて亡命して来た共産主義者にまで及ぶことになった。
大粛清は、当時のソビエト連邦(ソ連)の最高指導者ヨシフ・スターリンが1930年代にソ連邦でおこなった大規模な反対陣営に対する政治弾圧を指す。スターリンに対抗したと看做された者は全て見せしめ裁判でスパイ罪などの自白を強要され死刑の宣告を受けたもので、その対象は幹部政治家のみならず、一般党員や民衆にまで及んだ。その目的はスターリンが自分の政敵を殺すこと、なかなか進まぬ経済の発展への大衆の不満を「裏切り者への憎しみ」に向けてそらすことであった。この粛清はついには革命を成功させた赤軍の英雄や、尊敬されている芸術家、そして海外からソ連に安全を求めて亡命して来た共産主義者にまで及ぶことになった。
大粛清が1938年後半にようやく収まったのは、虐殺によって優秀な人間が殺され、国家機能に支障を来たすほどになり、またナチスの脅威が現実のものとなったので、国民の不満をナチスに対する憎しみに向けることが可能になったからである。1938年末になると、スターリンはこれまで大粛清の中心的組織であった秘密警察NKVDを批判し、弾圧することになった。皮肉なことに、あれだけたくさんの人間を死に追いやった秘密警察の関係者も次々と殺害され、NKVD関係の人間でスターリン時代を生き残れた者は殆どいなかったという。