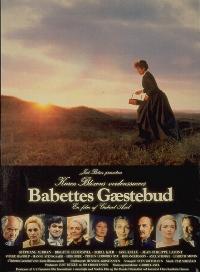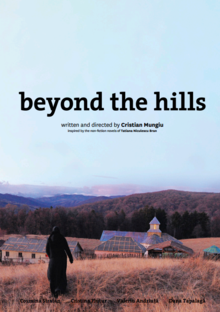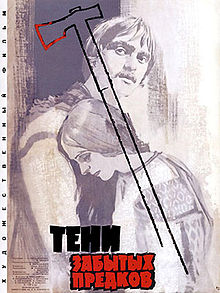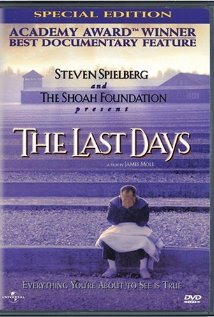『戦艦ポチョムキン』は、1905年のロシア帝国支配時に起こった水兵の反乱を、ソ連政権下の1925年に、共産革命の栄光の第一歩として描くプロパガンダ映画である。そのあまりのプロパガンダぶりには唖然とするが、同時に1925年にこれだけの斬新な映画を作ったセルゲイ・エイゼンシュテイン監督の鬼才にも唖然としてしまう。
『戦艦ポチョムキン』は、1905年のロシア帝国支配時に起こった水兵の反乱を、ソ連政権下の1925年に、共産革命の栄光の第一歩として描くプロパガンダ映画である。そのあまりのプロパガンダぶりには唖然とするが、同時に1925年にこれだけの斬新な映画を作ったセルゲイ・エイゼンシュテイン監督の鬼才にも唖然としてしまう。
ロシア帝国は、不凍港を求めて常に南下政策を採用し、1878年の露土戦争の勝利によってバルカン半島における権威を獲得した。ロシアの拡大を警戒するドイツ帝国の宰相ビスマルクは列強の代表を集めてベルリン会議を主催し、ロシアの勢いを牽制することに成功した。これによりロシアはバルカン半島での南下政策を断念し、進出の矛先を極東地域に向けることになり、その結果として1904年に日露戦争が起こったといえよう。アジアに権益を持つイギリスは、ロシアのアジア進出を怖れ、日英同盟に基づき日本への軍事、経済的支援を行ったが、独英に苦い思いを持つフランスは露仏同盟を結んで、両国に対抗した。日本側は当時は日本に好意的であったアメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトに和平交渉を依頼したが、ロシア側は当時無敵を誇っていたバルト海に本拠を置くバルチック艦隊を送ることを決定し、ルーズベルトの和平交渉を拒否した。
バルチック艦隊は7ヶ月に及びアフリカ大陸沿岸を巡回して日本へ向かった。アフリカの英独植民領からの食料や燃料支給の拒否は予想していたが、頼りにしていた仏領からの支援もままならず、大変苦しい航海を続けなければならなかった。実はイギリスとフランスは日露戦争開戦直後の1904年4月8日に英仏協商を結んでいたのである。1905年の5月27日に連合艦隊と激突した日本海海戦でバルチック艦隊はその艦艇のほとんどを失い、司令長官が捕虜になるなど壊滅的な打撃を受け、この海戦は日本海軍の一方的な圧勝に終わった。時を同じくして6月14日に黒海に駐留していた戦艦ポチョムキンで水兵の反乱が起きたので、ロシアも早期に日露戦争を終結する必要に迫られるようになった。
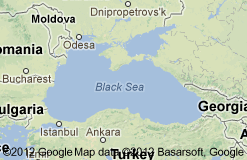 ロシアは露土戦争以前の1821年に勃発したギリシア独立戦争で、ギリシャのオスマン帝国からの独立を支援し、単独でトルコと開戦し勝利を収め、1829年のアドリアノープル条約で黒海沿岸地域をトルコから割譲し、ロシア船舶がボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡を自由に通行することを承認させた。ロシアの南下をおそれた英仏は1840年にロンドン会議を開き、1841年の国際海峡協定で、ロシアの船舶のボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡の通行は廃棄された。つまり、ロシアの軍艦は両海峡を越えて地中海に出ていくことが国際的に禁止されたのである。だから黒海にあるロシア海軍艦隊は日露戦争の時も出兵ができなかったのである。ポチョムキンはその黒海艦隊の一つであった。
ロシアは露土戦争以前の1821年に勃発したギリシア独立戦争で、ギリシャのオスマン帝国からの独立を支援し、単独でトルコと開戦し勝利を収め、1829年のアドリアノープル条約で黒海沿岸地域をトルコから割譲し、ロシア船舶がボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡を自由に通行することを承認させた。ロシアの南下をおそれた英仏は1840年にロンドン会議を開き、1841年の国際海峡協定で、ロシアの船舶のボスフォラス海峡・ダーダネルス海峡の通行は廃棄された。つまり、ロシアの軍艦は両海峡を越えて地中海に出ていくことが国際的に禁止されたのである。だから黒海にあるロシア海軍艦隊は日露戦争の時も出兵ができなかったのである。ポチョムキンはその黒海艦隊の一つであった。
この映画では、ポチョムキン艦上で水兵による武装蜂起が発生し、反乱を起こした水兵たちは士官を処刑して革命を宣言し、ウクライナの港湾都市オデッサに向かう。ポチョムキンを歓迎するオデッサの市民に対し、政府軍によるオデッサ市民の大虐殺が起こり、ロシア政府軍艦隊がポチョムキン鎮圧のために向けられる。しかし、政府軍艦隊の水兵たちはポチョムキンの水兵たちを兄弟と呼び、心を通わせるところを描き、革命の端緒の反乱を栄光を持って描く。しかし、この映画、どこまで事実を反映しているのだろうか。
 まず映画史上に残る名場面と絶賛されるオデッサの階段の虐殺は史実ではないらしい。この階段自体は実際にオデッサにある、不思議なデザインの階段である。階段に立って下を見下ろす人には踊り場だけ見えて階段は見えない。
まず映画史上に残る名場面と絶賛されるオデッサの階段の虐殺は史実ではないらしい。この階段自体は実際にオデッサにある、不思議なデザインの階段である。階段に立って下を見下ろす人には踊り場だけ見えて階段は見えない。 しかし階段を下から見上げる人には、階段だけ見えて、踊り場は見えない。
しかし階段を下から見上げる人には、階段だけ見えて、踊り場は見えない。 海から階段を見上げると階段が実際より長いように見せ、陸から階段を見下ろすと下までの距離は短いように思われる。
海から階段を見上げると階段が実際より長いように見せ、陸から階段を見下ろすと下までの距離は短いように思われる。 このオデッサの階段の虐殺のシーンがあまりにも古典として定着されてしまったので、歴史上の史実のようになってしまったのだ。オデッサの当局はポチョムキンの行動には否定的で、ポチョムキンが停泊することを許可しなかった。
このオデッサの階段の虐殺のシーンがあまりにも古典として定着されてしまったので、歴史上の史実のようになってしまったのだ。オデッサの当局はポチョムキンの行動には否定的で、ポチョムキンが停泊することを許可しなかった。
ポチョムキンを鎮圧しに行った艦隊がポチョムキンに砲火しなかったのは事実である。司令官代理に任命されたクリーゲル海軍中将は、自分が率いる鎮圧艦隊の中の水兵にはポチョムキンの反乱に賛成している者が多く、ポチョムキン砲火の命令をすると、自分の生命が危ういどころか全鎮圧艦隊の水兵が反乱を起こすことを感じ取り、何らの行為もせずポチョムキンから離れたのである。鎮圧艦隊の水兵たちは上官たちから禁じられていたにも拘らず、甲板上に出て接近するポチョムキンに歓声や挨拶を送った。何と、そのうちの一艦である装甲艦ゲオルギー・ポベドノーセツの水兵たちは自分たちの上官をたちを逮捕し、ポチョムキン蜂起に合流したのである。もう一つの戦艦シノープでは、ポチョムキンへの合流に賛成する派閥と反対派閥とが議論し、後者が勝ちポチョムキンへの参加は起こらなかった。
ポチョムキンで反乱した水兵たちは、その後どうなったのか?
ポチョムキンのもとに留まった装甲艦ゲオルギー・ポベドノーセツでは、すぐに水兵たちのあいだでの仲間割れが生じた。叛乱へ安易に同調したことを後悔した者たちが艦長や士官らを釈放し、翌日には叛乱の首謀者68名を引き渡した。オデッサから停泊を拒否されたポチョムキンはルーマニアのコンスタンツァに到着したが、ルーマニア政府はポチョムキンに必要物資を提供するのを拒んだ。ポチョムキンの水兵はルーマニアで降伏し、戦艦ポチョムキンはルーマニア政府によりロシア政府に返還された。大部分の水兵は政治犯としてルーマニアに亡命することを選び、1917年にロシア革命で共産党政権が樹立するまでルーマニアに留まった。また何人かはそこからさらに海外逃亡を図った者もいる。彼らの逃亡先はアルゼンチンなどの南米であり、またトルコ経由で西欧に向かった者もいた、
映画の中のオデッサの市民の反政府デモのシーンでは「処刑執行人、専制政府、ユダヤ人をやっつけろ!!」と叫ぶ市民が、「仲間で喧嘩をするのはよそう」となだめるユダヤ人をリンチするシーンまである。そのユダヤ人は金持ちそうで、憎たらしく描かれている。この映画を作製したセルゲイ・エイゼンシュテインがユダヤ人であるということを考えると、全く驚くが、これが当時のロシア人のユダヤ人に対する感情だったのかもしれない。
『戦艦ポチョムキン』の大成功により、セルゲイ・エイゼンシュテインはハリウッドに招かれ1930年からアメリカで暮し、ウォルト・ディズニーやチャーリー・チャップリンと親しく交際するようになるが、彼の映画人としてのアイディアはハリウッドで活用されることはなく、結局彼は一つの目に見える業績もなくソ連に戻ることになった。一体彼はアメリカで何をしていたのだろうかとすら思う。
 セルゲイ・エイゼンシュテインが帰国した時にはスターリンの大粛清が始まり、その粛清が芸術家にも及んでいた時であった。セルゲイ・エイゼンシュテインは完璧には社会主義リアリズムに合致しない芸術味豊かな映画を作り、またアメリカに長期滞在していてアメリカ人の友人も多かったのでスパイ罪の嫌疑がかかってもおかしくない状況であったが、彼はこの粛清も無事乗り切ったようで、どういうわけか彼の上司にあたるボリス・シュマトスキーが粛清にあい、処刑されている。ここには何故か大きな暗黒の疑問符が漂っているのである。
セルゲイ・エイゼンシュテインが帰国した時にはスターリンの大粛清が始まり、その粛清が芸術家にも及んでいた時であった。セルゲイ・エイゼンシュテインは完璧には社会主義リアリズムに合致しない芸術味豊かな映画を作り、またアメリカに長期滞在していてアメリカ人の友人も多かったのでスパイ罪の嫌疑がかかってもおかしくない状況であったが、彼はこの粛清も無事乗り切ったようで、どういうわけか彼の上司にあたるボリス・シュマトスキーが粛清にあい、処刑されている。ここには何故か大きな暗黒の疑問符が漂っているのである。
第二次世界大戦後、セルゲイ・エイゼンシュテインと親友だったことから、ウォルト・ディズニーやチャーリー・チャップリンはマッカーシー上院議員が権限を持って遂行した「赤狩り」の容疑者に挙げられる。ウォルト・ディズニーは無実を勝ち取ったが、チャーリー・チャップリンは結局国外追放となったのである。