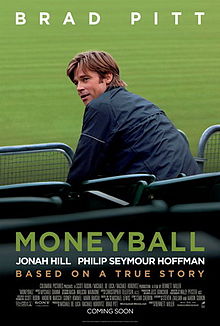ニュールンベルグ裁判は史実である。しかしこの映画は、史実の中の歴史的なエッセンスを基に物語を作成し、冷戦下のアメリカの良心という観点から、第二次世界大戦後の世界を描こうとした試みであるといえるだろう。
ニュールンベルグ裁判は史実である。しかしこの映画は、史実の中の歴史的なエッセンスを基に物語を作成し、冷戦下のアメリカの良心という観点から、第二次世界大戦後の世界を描こうとした試みであるといえるだろう。
第二次世界大戦終了後、戦勝国である米英仏露の軍部指導者は、ドイツの戦争犯罪人を裁くためにニュルンベルクに集まった。1945年に開始された前期の裁判は戦争を導いたドイツの最高クラスの指導者を一方的に断罪し、厳しい判決が下されたが、この映画の舞台となった1948年のニュルンベルク継続裁判になると、裁判を取り巻く世界情勢が微妙に変わっていた。米英仏にとっての脅威はもはやドイツではなく、ソ連であった。ソ連軍はドイツ東部を占拠し、さらにドイツ全土の占拠を視野に置いていると思われた。米英仏はソ連がドイツを支配下に置けば、全ヨーロッパがなし崩しに共産化すると判断し、今や米英仏の関心は、ドイツ人を裁くよりドイツをソ連から守り、共産化されることを防ぐことであった。
 映画はアメリカの地方裁判所の判事ヘイウッド(スペンサー・トレイシー)が、ニュルンベルク継続裁判の一つのケースの主任判事に任命され、ニュールンベルグに赴く所から始まる。彼が任命された理由は、このケースはドイツの最高クラスの法律家を裁くものであり、特に国際的に高名で敗戦当時はナチの法務大臣であったエルンスト・ヤニング博士(バート・ランカスター)が被告の一人であったので、誰もその裁判の判事になりたがらず、無名で実直なヘイウッド判事にその任務が押し付けられたのであった。
映画はアメリカの地方裁判所の判事ヘイウッド(スペンサー・トレイシー)が、ニュルンベルク継続裁判の一つのケースの主任判事に任命され、ニュールンベルグに赴く所から始まる。彼が任命された理由は、このケースはドイツの最高クラスの法律家を裁くものであり、特に国際的に高名で敗戦当時はナチの法務大臣であったエルンスト・ヤニング博士(バート・ランカスター)が被告の一人であったので、誰もその裁判の判事になりたがらず、無名で実直なヘイウッド判事にその任務が押し付けられたのであった。
 ヘイウッド判事とニュルンベルクに滞在しているアメリカの軍人たちは、ドイツの伝統とその文化の奥深さに感動する。戦後の貧しさの中でも人々は美味しいビールを飲み、酒場では美しい合唱を楽しみ、ピアノやオペラの演奏に心を震わせる。人々の心は優しく、「ドイツ人は世界が信じるような獣ではない」と一人一人が証明しようとしているかのようだ。戦勝国として入って来た軍人たちは、「僕たちは、まるで美しい宮殿に土足で踏み入るボーイスカウトのようなものだな」と自嘲してしまうのである。戦争さえなければドイツはアメリカ人にとっての文化的憧れであっただろうに。そんなヘイウッド判事や、検事を勤めるローソン大佐(リチャード・ウィドマーク)に国家のトップから、裁判を早々に切り上げて、ドイツを味方につけるために厳しい判決をくださないようにという暗黙のプレッシャーがかかってくる。
ヘイウッド判事とニュルンベルクに滞在しているアメリカの軍人たちは、ドイツの伝統とその文化の奥深さに感動する。戦後の貧しさの中でも人々は美味しいビールを飲み、酒場では美しい合唱を楽しみ、ピアノやオペラの演奏に心を震わせる。人々の心は優しく、「ドイツ人は世界が信じるような獣ではない」と一人一人が証明しようとしているかのようだ。戦勝国として入って来た軍人たちは、「僕たちは、まるで美しい宮殿に土足で踏み入るボーイスカウトのようなものだな」と自嘲してしまうのである。戦争さえなければドイツはアメリカ人にとっての文化的憧れであっただろうに。そんなヘイウッド判事や、検事を勤めるローソン大佐(リチャード・ウィドマーク)に国家のトップから、裁判を早々に切り上げて、ドイツを味方につけるために厳しい判決をくださないようにという暗黙のプレッシャーがかかってくる。
 ローソン大佐を迎え撃つ被告の弁護士ロルフ(この映画でアカデミー賞主演男優賞を受賞したマクシミリアン・シェル)は鋭い理論でローソン大佐の主張を次々に論破していく。ローソン大佐はユダヤ人の強制収容所を解放した自分の経験から、ユダヤ人の連行を文書の上で承認した法律学者を徹底的に裁こうとする。反対にロルフは「ドイツと独ソ不可侵条約を結んだソ連、虐殺や不法占領を行ったソ連の戦争責任はどうなのか。共産主義を抑えるためにヒットラーに同意した英国のチャーチルの戦争責任はどうなのか」と激昂する。それは、ニュールンベルグ裁判で戦勝国の横暴を黙って耐えなければならなかったドイツ人の無念を代弁していたのである。
ローソン大佐を迎え撃つ被告の弁護士ロルフ(この映画でアカデミー賞主演男優賞を受賞したマクシミリアン・シェル)は鋭い理論でローソン大佐の主張を次々に論破していく。ローソン大佐はユダヤ人の強制収容所を解放した自分の経験から、ユダヤ人の連行を文書の上で承認した法律学者を徹底的に裁こうとする。反対にロルフは「ドイツと独ソ不可侵条約を結んだソ連、虐殺や不法占領を行ったソ連の戦争責任はどうなのか。共産主義を抑えるためにヒットラーに同意した英国のチャーチルの戦争責任はどうなのか」と激昂する。それは、ニュールンベルグ裁判で戦勝国の横暴を黙って耐えなければならなかったドイツ人の無念を代弁していたのである。
裁判の最大の焦点はヤニング博士がニュルンベルク法の基で犯罪を犯したかどうかであった。ニュルンベルク法はナチが作った法律で、ユダヤ人とドイツ人の交流を犯罪として定義している。ヤニング博士は判事として、少女イレーネ・ホフマン(ジュディ・ガーランド)と交際したという罪状でユダヤ人の老人を死刑に、その罪状を否定するイレーネを偽証罪で懲役に課していたのだ。
ヘイウッド判事は人々の予測に反して被告全員に有罪判決を下し、終身刑に課した。彼は検察側は実際の犯罪が行われたことを『beyond a reasonable doubt』まで証明し、被告たちの名による執行命令の文書がない限りはこの犯罪が行われなかったから、被告たちは実際に手を下さなかったが法的な共謀者であるという理論であった。これに対し、裁判の副審を勤めた米国人の判事は弁護士ロルフの理論に同意し、被告はドイツの国家法であるニュルンベルク法に従ったまでであり、もしこの法律に従わなければ被告は国家に対する謀反の罪を犯すことになったとし、主審であるヘイウッド判事の判決に反論を加えた。
ここには英米で行われている普通法(Common Law)と独仏で行われている成文法の解釈の対立という図式もみられる。ヘイウッド判事は普通法の国米国で法律を学んでいるから、裁判官による判例を第一次的な法源とし、裁判において先に同種の事件に対する判例がある時はその判例に拘束されるとする判例法主義の立場から有罪判決に至った。しかしもちろん英米にも成文法があるから、裁く領域に成文法が存在する場合には成文法の規定が普通法よりも優先する。成文法は基準がは明確だし、ナポレオン法典のように長期間模範になる法律もあるが、ニュルンベルク法はどうであるだろうか?狂った指導者が狂った成文法を作ることは可能であることを、ニュルンベルク法は示唆しているのではないだろうか。たとえば、米国でも新しい法律を作ることは可能である。しかし、その法律は議員の多数の賛成を得なくてはならないし、もしそれが憲法に反対していたら司法から否決されるのである。
ヘイウッド判事の有罪判決はドイツ人もアメリカ人も失望させた。人々は被告はニュルンベルク法に従っただけであり、責められるのは法律そのものだと信じていた。また同時期の他の裁判は概ね被告が無罪となり、たとえ有罪であったとしても刑が非常に軽かったからだ。ロルフはヘイウッド判事に面と向かい「被告は全員5年以内に無罪放免されるだろう。アメリカ人はきっと近い将来ソ連軍に不法裁判で裁かれるような事態に置かれるかもしれないから、せいぜい心せよ」という言葉を投げかけて去って行く。ヤニング博士の要望で個人として彼と対面したヘイウッド判事は「あなたは有罪だ。なぜならば、イレーネ・ホフマンの裁判に臨む前にあなたは既に有罪判決を決めていたからだ」と述べる。ヘイウッド判事も、無罪判決を下したら、自分の判決が判例となり、将来文書で死刑を宣告した人間は自分の判例を根拠にして無罪になるという拡大解釈が起こるのを防ぎたかったのであろう。
 マレーネ・ディートリッヒがニュールンベルグ裁判で処刑された将軍の未亡人として出演している。彼女の夫は戦後すぐの戦勝国の集団リンチのようなニュールンベルグ裁判で有罪となったが、もし裁判が1948年に行われていたら無罪になった可能性もあると映画では示唆されている。ヘイウッド判事と友情を育てた夫人は、夫妻ともにヒットラーを憎み、夫はドイツ国民を守るために戦ったのであり、国民の大部分はナチが何をやっていたのかは知らされていなかったと述べ、ドイツ国民の魂をヘイウッドに伝えようとする。
マレーネ・ディートリッヒがニュールンベルグ裁判で処刑された将軍の未亡人として出演している。彼女の夫は戦後すぐの戦勝国の集団リンチのようなニュールンベルグ裁判で有罪となったが、もし裁判が1948年に行われていたら無罪になった可能性もあると映画では示唆されている。ヘイウッド判事と友情を育てた夫人は、夫妻ともにヒットラーを憎み、夫はドイツ国民を守るために戦ったのであり、国民の大部分はナチが何をやっていたのかは知らされていなかったと述べ、ドイツ国民の魂をヘイウッドに伝えようとする。
マレーネ・ディートリッヒの生涯がこの将軍夫人のキャラクターを生んだと言えよう。ドイツ出身の彼女は渡米後、ユダヤ人監督スタンバーグとのコンビでハリウッドのトップスターになった。アドルフ・ヒトラーはマレーネが気に入っておりドイツに戻るように要請したが、ナチスを嫌ったマレーネはそれを断って1939年にはアメリカの市民権を取得したため、ドイツではディートリッヒの映画は上映禁止となる。その後彼女は身の危険を冒してまで、アメリカ軍人の慰問に尽くした。
戦後アメリカを訪問した女優の原節子はマレーネ・ディートリッヒに紹介された時の感想を次のように述べている。映画ではとても美しく見えるのですが、実際に会ったディートリッヒはさばさばとあっさりした人で、顔も平板で映画での怪しい美しさが感じられませんでした。綺麗な人という印象は全くありませんでした・・・・
マレーネ・ディートリッヒの美しさは、そのたぐい稀なプロフェッショナリズムと人生への決意から来ているのではないだろうか。ディートリッヒがこの映画で若く美しい未亡人を演じた時、彼女は既に60歳であったのだ。原節子ももちろん戦争中は(他の日本人がそうであったように)大変苦労したであろうが、マレーネ・ディートリッヒがどれだけのものを乗り越えて来たのかを考えることはなかったであろうと思わされるような彼女の発言であった。